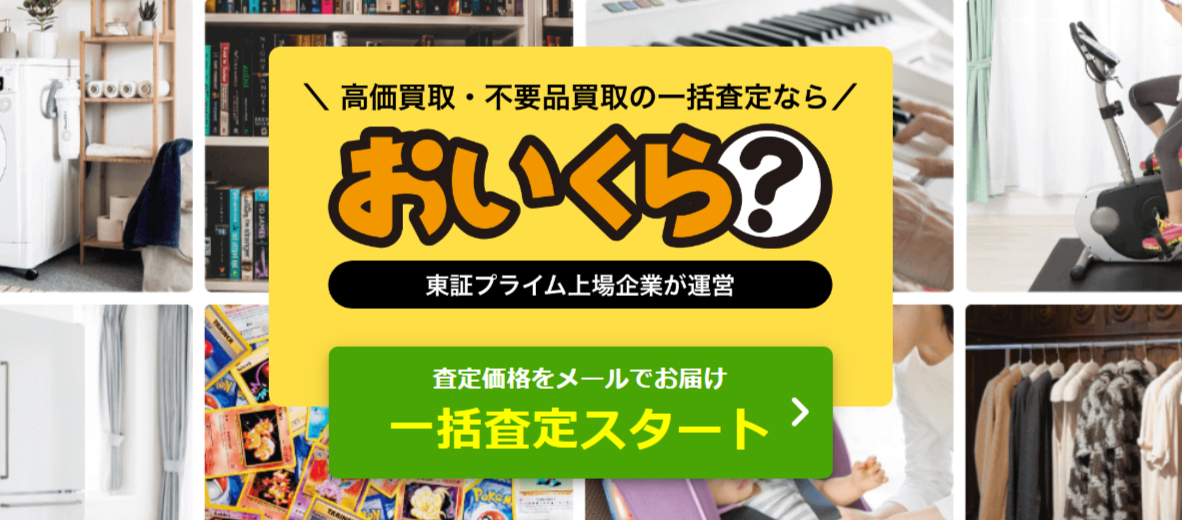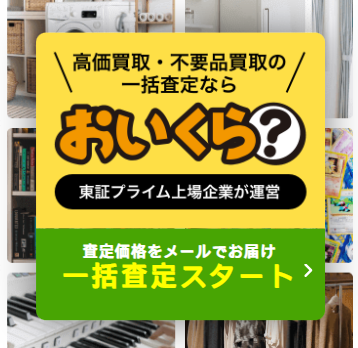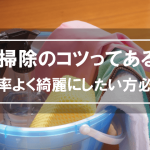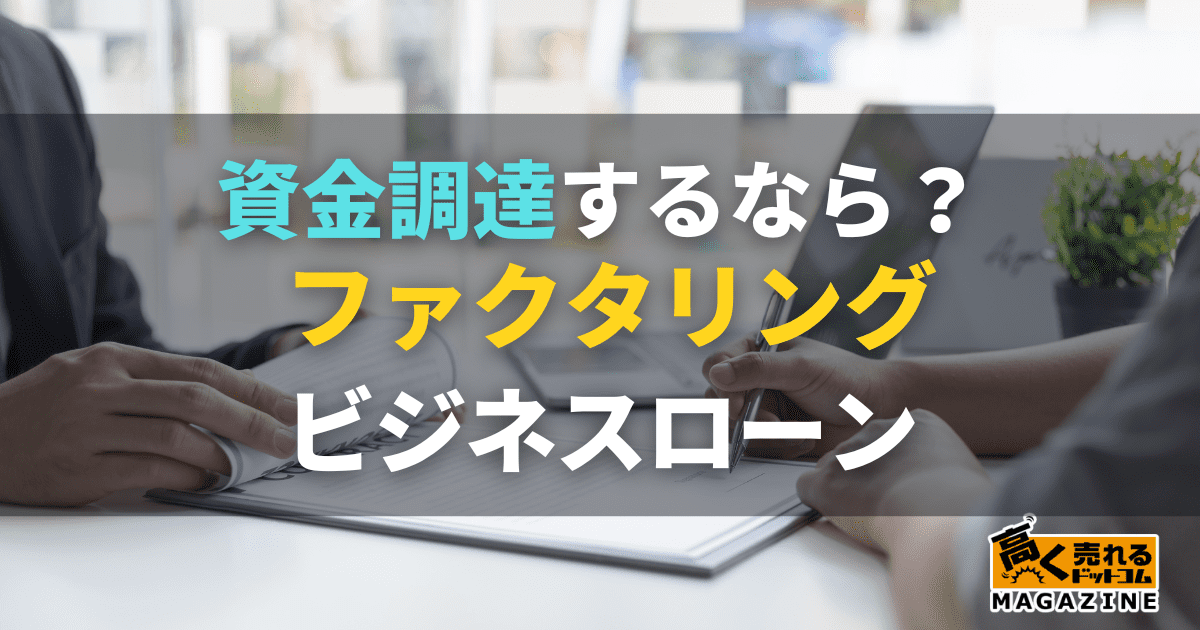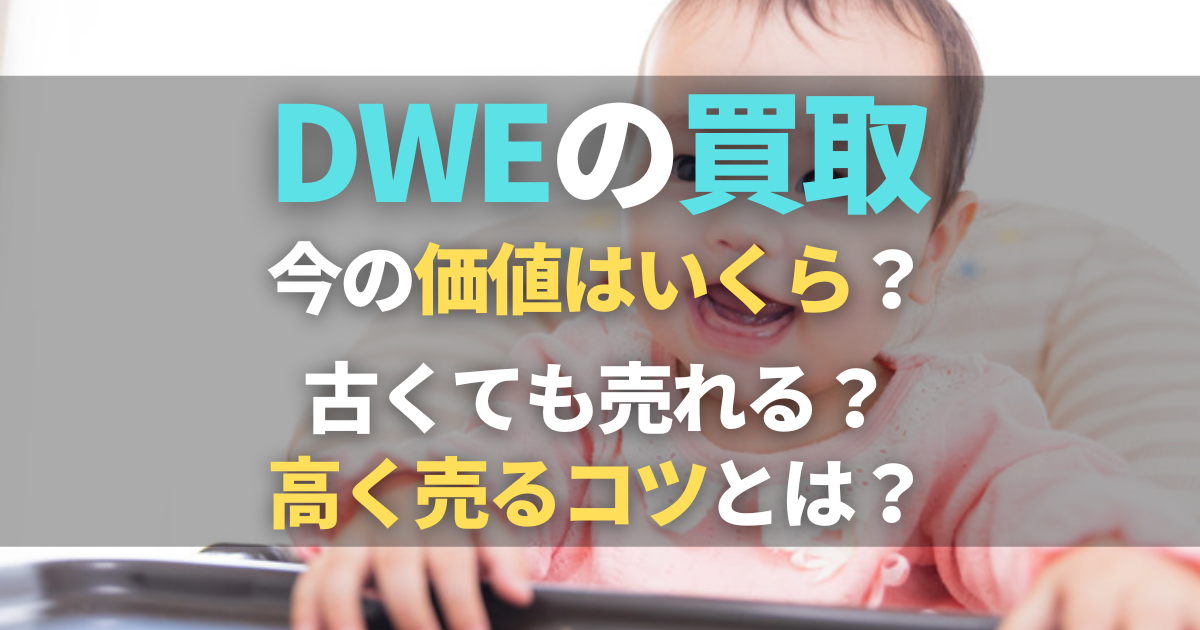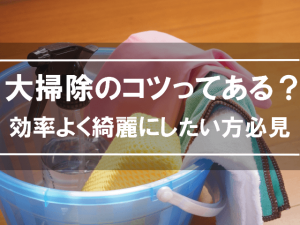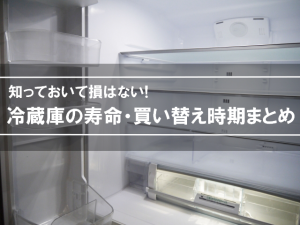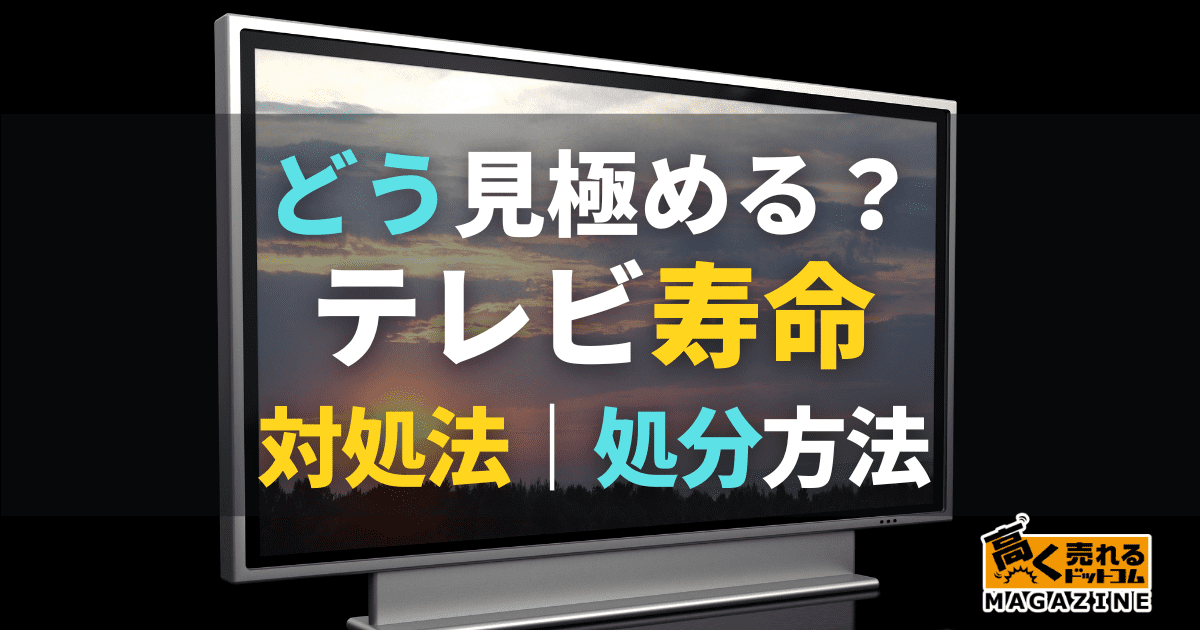- ニュース情報・リユース関連
年末大掃除の仕方まとめ|捨てるのに迷う不用品はどうする?
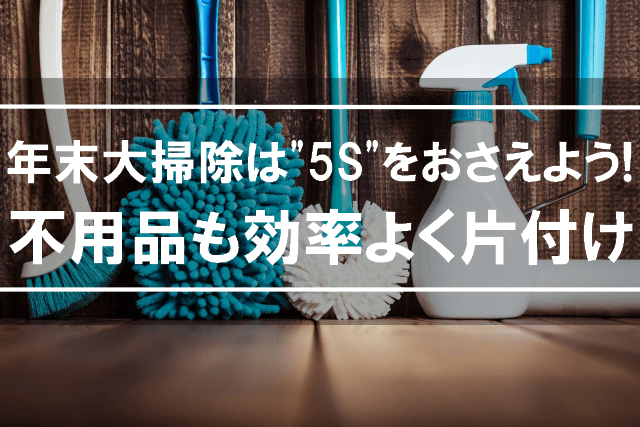
※当記事はアフィリエイト広告を含みます。
※「高く売れるドットコム」「おいくら」は弊社マーケットエンタープライズが運営するサービスです。
目次
※相場情報は実際の買取価格と異なる可能性がございます。
5Sを押さえれば大掃除は楽になる

5Sとは、整理整頓や清掃に組織をあげて取り組み、徹底してきれいにする活動です。
5Sの概念は工場や職場などビジネスシーンで使われることが多いものですが、家庭での掃除の際にも非常に役に立ちます。大掃除で5Sを取り入れるポイントをご紹介します。
【整理】不用品を捨てるか迷ったら

整理は大掃除の第一歩です。お子さんの学校関連のプリントや文具用品、趣味の書籍や整髪料など、知らない間に増えているものにお心当たりがある方も多いのではないでしょうか。
そういったものを必要なものと不要なものとに分け、不要なものを手放すのが「整理」です。手元に残るのが必要なものだけになれば探し物の時間も省けます。また必要なのに無いものなども再確認することができます。整理は以下の手順で行います。
- プリント類、衣類、書籍など、同じ種類のものを1か所に集める
- 「いるもの」「いらないもの」「判断のつかないもの」に分けていく
- 「いらないもの」は自治体のルールに従い破棄する
- 「判断のつかないもの」は一定期間おいておき、使わなくても困らないようなら破棄する
整理の際に困るのが、使わないのに捨てられないものがあること。お子さんが描いた絵やプレゼントされたものなどは思い入れもあり、手放しづらいものです。そういった思い出の品は、写真に残すのがおすすめです。後で見返すこともでき、場所も取りません。思い出はそのままに、整理を進めることができます。
さらに、捨てるのに忍びない食器類や書籍などは中古品の買取業者に売却して手放すという手もあります。誰かに使ってもらえるので罪悪感を減らせます。もしかしたら思わぬ高値になることもあり、一石二鳥です。
たとえば「高く売れるドットコム」なら使わなくなったベビー用品から高価なブランド品まで、さまざまなアイテムを買い取ってくれます。Webサイトから無料で見積もり依頼もできるため、気になる方はぜひチェックしてみてください。
安心の上場企業がご自宅まで!
\10万品目買取でまとめ売り可/
高く売れるドットコムで
不用品の出張買取を依頼する
【整とん】便利グッズでもう散らからない

次のステップは整とんです。整理で手元に残した必要なものを、本来あるべきところに戻します。「ペンはペン立てに、書籍は本棚に」という当たり前のことですが、なかなかできていない方も多いのでは。
整理で必要なものだけになっても、いざ必要になったときにどこにしまいこんだかわからないようでは「整とんされている」とはいえません。使うシーンや動線を考えて、便利でかつ片付けやすいところに必要なものを収納するようにしましょう。
しかし、収納場所がそこまでたくさんあるわけではなく、しまいたいところにものを収納できないこともあるでしょう。そうしたときにぜひ使いたいのが、小さなスペースにもたくさん収納できる便利グッズです。
たとえばクローゼットなら、8連ハンガーや10連ハンガーといった、1つのフックにたくさんの衣類が掛けられるハンガーがおすすめです。靴をたくさん持っている場合は、1足分のスペースに2足置けるシューズスタンドなどを活用すると収納力が倍になります。
こうした収納グッズは日々進化を遂げて、ますます便利になっています。大掃除をきっかけに、自分のニーズに合った収納グッズを探してみるのもよいかもしれません。
安心の上場企業がご自宅まで!
\10万品目買取でまとめ売り可/
高く売れるドットコムで
不用品の出張買取を依頼する
【清掃】上から下に、奥から手前に

清掃というのは、私たちが普段掃除と聞いてイメージするものです。日常生活で使う場所やものに汚れや不具合がないかを確認して汚れを落とします。
清掃には、「上から下に、奥から手前」にという基本があります。天井や照明のほこりをモップやはたきで落とし、棚やテーブルの上などをきれいにし、最後に床掃除をするのがコツです。この手順が守られていないと、床掃除が終わった後にほこりや汚れが床に落ち、再度床を掃除しなければならない事態に陥ります。
また、掃除の二度手間を防ぐためには、奥から手前に掃除を進めるのも大切なことです。引き出しや棚などは、ドア付近よりも奥のほうが空気が動かず、汚れがたまりがちなもの。
奥から手前に拭き掃除を進めることで、汚れの取りこぼしなくきれいにできます。なお、棚だけではなく部屋全体も同じように奥から手前に掃除をしましょう。雑巾がけなどをする際も奥から入り口に向かって拭き掃除すれば、きれいになったところを踏まないですみます。
ただし、窓ふきは逆に下から上に進めるのが鉄則です。洗剤をつけて上から拭いていくと、汚れた洗剤液が下に流れてしまい、汚れがとれなくなってしまう可能性があるため、お気をつけください。
そして、作業は軽い汚れからひどい汚れへと進めていくのもポイントです。全体的に軽い汚れをきれいにしてから、局地的なひどい汚れをきれいにしていくと、ひどい箇所の汚れを広げてしまうことなく清掃できます。
この順番を守ると、使う洗剤も段階的に強くしていくことができるため、不必要に強力な洗剤を使いすぎることも ありません。
安心の上場企業がご自宅まで!
\10万品目買取でまとめ売り可/
高く売れるドットコムで
出張買取を依頼する
【清掃】汚れの種類を見極めて

清掃においては、順序だけではなく汚れ落としも大切なポイントです。キッチンの換気扇や落ちにくい風呂場の水垢などは普段先延ばしにしてしまっていることも多く、ぜひ大掃除の機会に掃除したいもの。それも時間が限られているので、できるだけ汚れに効く洗剤を選びたいところです。
汚れを落とす際に確認したいことが、その汚れが「酸性」か「アルカリ性」かということ。べたべたしがちな皮脂汚れやキッチンの油汚れなどは酸性で、ポットの水垢や石鹸カスはアルカリ性です。
汚れは中和させると溶けて落ちやすい性質があるため、酸性の汚れにはセスキ炭酸ソーダや重曹などのアルカリ性の洗剤を使用するとすっきり落とせます。 一方アルカリ性の汚れには、クエン酸など酸性の洗剤がよく効きます。洗剤を使う際は清掃する箇所の材木を傷めないよう、目立たないところで少量試してみてからにしましょう。
安心の上場企業がご自宅まで!
\10万品目買取でまとめ売り可/
高く売れるドットコムで
不用品の出張買取を依頼する
【清潔】プロに頼んで賢くきれいに

きれいにした箇所をきれいなままで維持できるようにするのが清潔です。せっかくきれいになっても、日々忙しい中ではどうしてもキッチンの換気扇などの清掃頻度が落ちてしまう家庭もあるのではないでしょうか。
そんなときには、無理せず家事代行などのプロの手を借りるというのも一案です。
忙しい家庭ならエアコン・台所・水回り・お風呂場など、気になるところをまるごとお任せしてしまうことで、ゆったりとお正月を迎えることができます。
プロならではの経験やノウハウももちろん、洗濯機のパン周りなど自分では見落としがちな箇所もきれいにしてくれます。
安心の上場企業がご自宅まで!
\10万品目買取でまとめ売り可/
高く売れるドットコムで
不用品の出張買取を依頼する
【しつけ】ルールを共有する

ビジネスシーンにおけるしつけとは「職場のルールを守り、きれいに使うように習慣づける」ことです。大掃除においては、家族のルールを決め、一人一人が家をきれいに使うよう習慣づけるというのが当てはまるかもしれません。
一人暮らしでも家庭があっても、きれいな状態を維持するのは難しいものです。特に小さなお子さんがいるご家庭では、ようやく部屋をきれいにしたと思っても、あっという間に散らかってしまいます。
大掃除でせっかくきれいになった状態を保つには、少しの労力で掃除を行えるように工夫することが欠かせません。
家の中の汚れというのは、ほこりや水滴を放置して油分などがくっついてしまい、除去しづらくなるケースが多いことをご存知でしょうか。
デザイン性の高いほうきを室内に掛けておく、洗面台に小さなスポンジを置いておくなどすると、ほこりや水滴が汚れになる前にすぐきれいにすることができます。それを家族内で共有し、習慣づけていくことでいつでもきれいな家を保てるでしょう。
さらに、小さなお子さんがいる家庭では、お子さん自身に片付けを促すというのもきれいな家を保つのに大切なポイントです。「つみき」「にんぎょう」など箱にラベリングしてお子さんが片付けやすい環境を整えてあげましょう。
安心の上場企業がご自宅まで!
\10万品目買取でまとめ売り可/
高く売れるドットコムで
不用品の出張買取を依頼する
不用品はまとめ売りで処分|おすすめ買取業者
せっかく綺麗に掃除しても、モノが多いと何だか片付いて見えませんよね。
使わなくなったのに場所を取るアウトドア用品やベビーカーなどは、いちいちゴミに出すよりまとめて売ってしまうのが手軽でおすすめです。
ここではおすすめの買取業者を紹介します。
高く売れるドットコム

| サービス名 | 高く売れるドットコム |
|---|---|
| WEB査定 | WEB査定はこちらから |
| 電話査定 | 0120-55-1387(※年末年始除く9:15~21:00) |
| 運営会社 | 株式会社マーケットエンタープライズ |
東証プライム上場企業の弊社マーケットエンタープライズが運営する「高く売れるドットコム」は、全国530万人の方にご利用いただいている総合ネット買取サービスです。買取方法は店頭買取・宅配買取・出張買取に対応しており、出張エリアは全国です。
買取対象商品は家電家具などの大型商品から貴金属やブランド品・骨董品・楽器・スマホ・パソコン・車・ファッションアイテムといった商品まで幅広く買取いたします。
点数が少なくてもお見積もりいたしますので、ぜひお気軽に電話[0120-55-1387]またはWEBからお問い合わせください。
買取にかかる手数料はすべて無料。査定料、出張料、キャンセル料、宅配送料など、お客様の負担金はいっさいかかりません。どなたさまにも安心してご利用いただける買取サービスです。
買取品目10万点
\まとめ売りでスッキリ/
高く売れるドットコムで
出張買取を依頼する
おいくら
出典:おいくら公式サイト
| サービス名 | おいくら |
|---|---|
| WEB査定 | WEB査定はこちらから |
| 運営会社 | 株式会社マーケットエンタープライズ |
「おいくら」は東証プライム上場企業の弊社マーケットエンタープライズが運営する一括査定サービスです。
一括査定サービスとは、全国の登録リサイクルショップ・買取店から一度にまとめて査定結果を取り寄せることができるサービスのこと。
複数の業者からの査定結果を手軽に比較できるため、より高い買取価格で商品を売却できるのです。
一括査定のほかに、出張買取に対応している地域の業者を検索できるサービスもご用意しております。
また、おいくらに参加している加盟店は弊社の審査を通過hした優良店だけです。そのため、他店で買取不可の品でも買取できる業者を見つけやすいシステムが整っています。
会員登録は不要で、電話番号を入力する必要はありません。個人情報が気になる方でも、安心して一括査定サービスをご利用いただけます。
おいくらなら
\一番高い買取業者が簡単に見つかる/
おいくらで
出張買取を依頼する
買取屋さんグループ
| サービス名 | 買取屋さんグループ |
|---|---|
| WEB査定 | WEB査定はこちらから |
| 運営会社 | 株式会社GRACE |
「買取屋さんグループ」の出張買取は全国対応です。電話またはメールで申し込むと、最短30分で出張買取に対応してくれます。急いでお片付けしたい方にとって、対応の早さはうれしいポイントですね。
買取対象となる品目は幅広く、家具家電・楽器・オーディオ・趣味の品などさまざまなジャンルの商品を扱っています。
査定は過去の実績やデータをもとにして適正価格で提示されます。査定料や出張料などはいっさい無料。キャンセル料もかかりませんのでご安心ください。
まとめ
大掃除を効率よく進めるポイントは、いるものといらないものを見直したり、使うシーンを考えながら正しく収納したりといった作業が重要になってきます。
またビジネスシーンでも使われる5Sを覚えておけば、大掃除でも活用できます。不用品の捨て方は、粗大ごみセンターに引き取ってもらう、リサイクルショップに持っていくなど、捨て方にも注意しましょう。
1人暮らしでも家庭があっても、きれいな部屋を維持するというのはなかなか大変なことです。家族やプロの手を借りながら、すっきりとした家を長く保てるように環境を整えていきましょう。