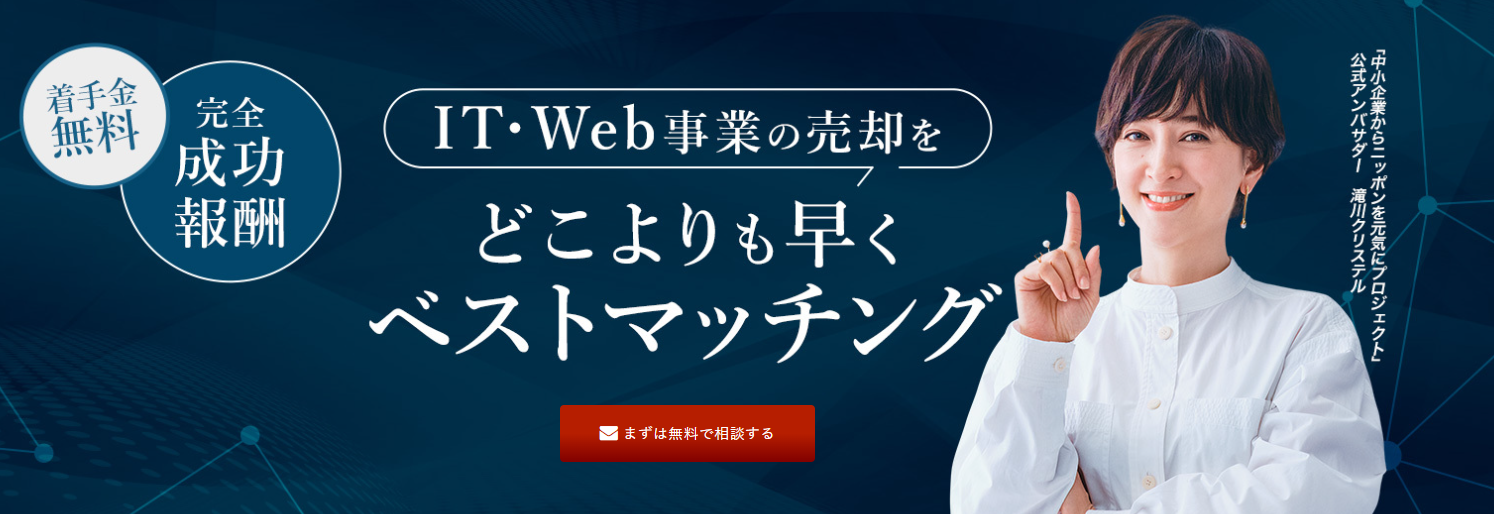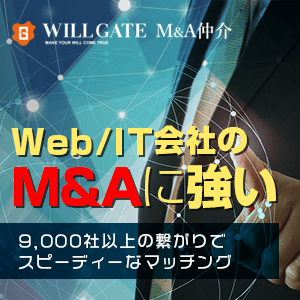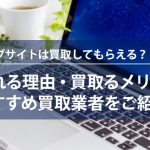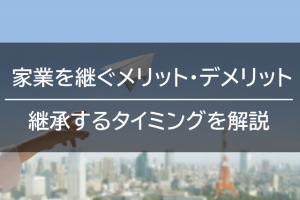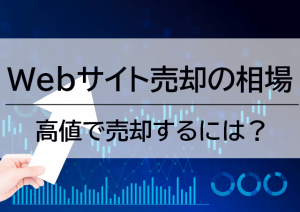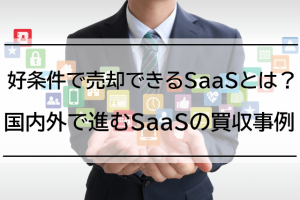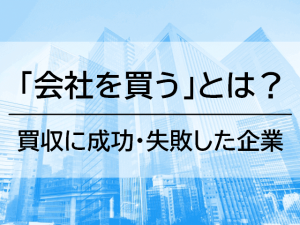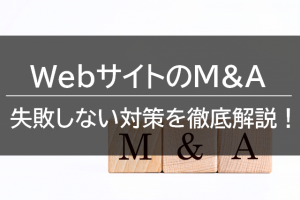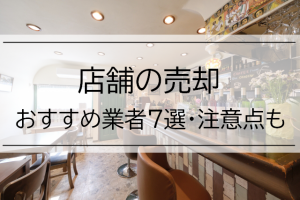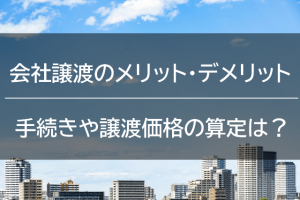- サイト売買・M&A
事業承継とは?5つの方法やメリットなど徹底解説
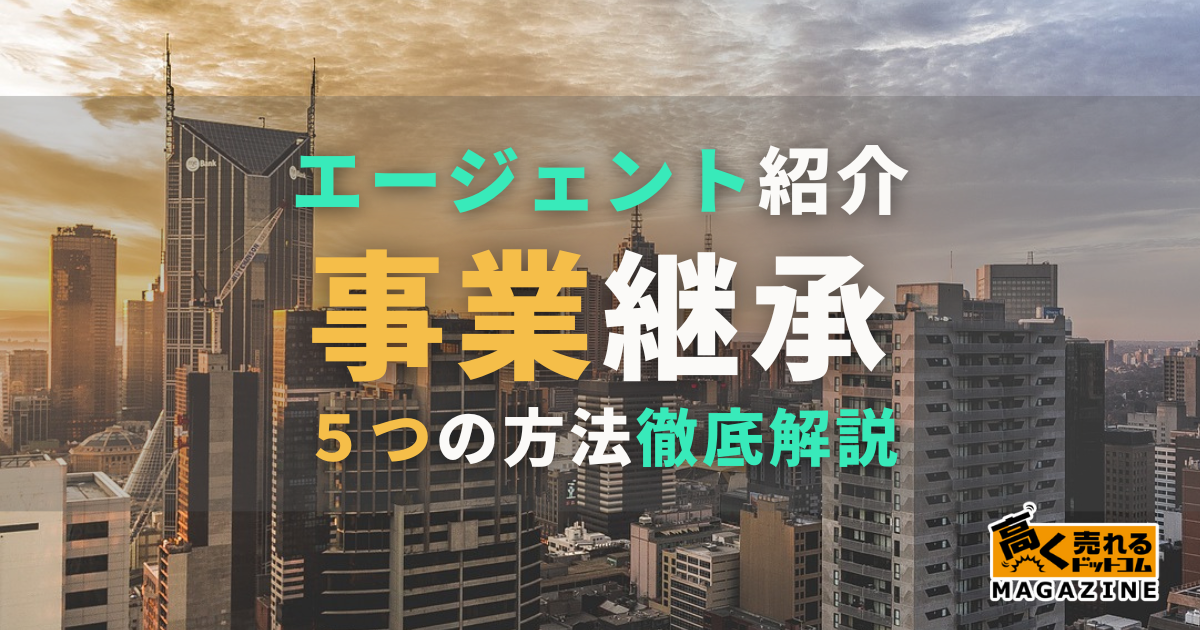
※当記事はアフィリエイト広告を含みます。
※「高く売れるドットコム」「おいくら」は弊社マーケットエンタープライズが運営するサービスです。
「事業承継」は、いかなる経営者にとっても決して避けて通ることのできない事柄です。
誰に引き継ぐのか、方法はどうするのか、事業継承に関わる重要な決定事項は数多くあります。
どこから手をつけていけばよいのか、いつから始めればよいかなど、事業継承に関してお悩みの方に、基本的な考え方から具体的な方法まで詳しくお伝えします。
輝かしいキャリアに傷がつくようなことのないよう、早めの準備が肝心です。
目次
サイト・事業売却をお考えの方へ
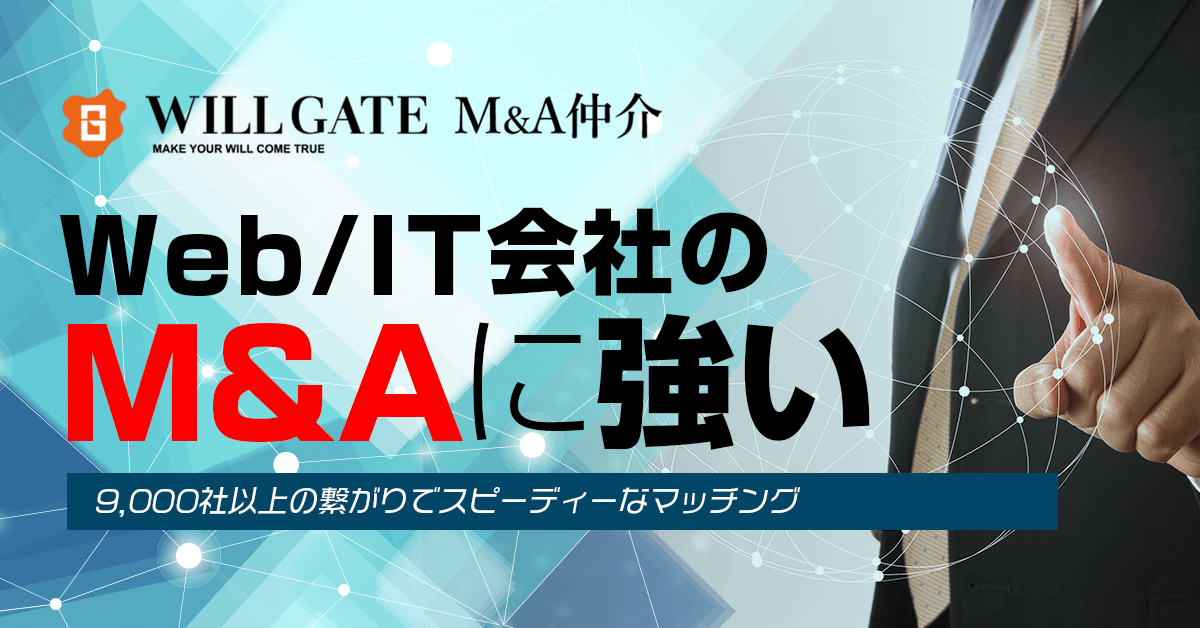
取引実績250社以上!
IT・Web事業領域の売却ならウィルゲートM&A
※相場情報は実際の買取価格と異なる可能性がございます。
事業承継おすすめエージェント2選
Willgate M&A
「Willgate M&A」はIT・Web事業のM&Aに精通している業者です。
Willgate M&Aの大きな魅力は買い手企業の数です。開始から僅か3年で買い手企業の掲載数が1,700社を超え、売り手と買い手のマッチングが叶いやすいサービスとなっています。
成約実績も44件と豊富に持っており、評価額40億円越えの成約実績も持っています。
数多くの成約実績を持っている理由として、有名企業の経営者との繋がりがあります。Willgate M&Aは17年に渡り、Webマーケティングに注力している7,400以上の企業の支援を行ってきました。
これらの取引実績や独自のネットワークから、現在では上場企業を含む9,100社以上との繋がりを持っています。これらの企業と密な連携を図る事でスピーディかつ適切なマッチングを可能にしています。
また、Willgate M&A自身も2度の事業譲渡、4度の事業譲受の経験が有るからこそ、経営者の気持ちを理解し、丁寧なサービスの提供を実現しています。
「IPOではなくバイアウトを検討している」「一部事業を清算し、新規事業への投資拡大をしたい」「大企業と組んで事業を拡大していきたい」などの悩みをお抱えの企業・事業主におすすめのサービスです
M&Aクラウド

出典:M&Aクラウド公式サイト
「M&Aクラウド」は買い手の責任者とすぐに会うことができるプラットフォームを提供している業者です。
IT上場企業の20%以上を買い手として掲載中です。大企業だけでなく、多くのベンチャー企業や中堅企業の掲載実績も豊富に持っているサービスです。
この他にも、DX(デジタル・トランスフォーメーション)に関心のある非上場企業も多く掲載しています。
「自社だけでは事業を次のステージに進めるのが難しい」
「会社や事業の売却方法が分からない」
などの悩みをお持ちの方におすすめのサービスです。
M&Aクラウドは買い手のM&Aニーズ・買収実績・独占インタビューなどを公開しており、M&A成立後のミスマッチが起こりにくいシステムになっています。
また、仲介業者が間に入ることが無いため、買い手と直接取引を行えます。マッチングから面談までの平均時間は1週間程度と、スピーディーに交渉を始められるのも大きな魅力です。
さらに、着手金や成約手数料を初め、プロのアドバイザーへの相談なども全て完全無料でご利用いただけます。
完全無料で利用できるプロのアドバイザーへの無料相談だけでもお試しください。
事業承継とは?

「事業承継」の言葉本来の意味は「会社や個人から事業を受け継ぐ」ことになりますが、一般的には「引退する経営者が、自ら選んだ後継者に事業を引き継ぐ」ことを指します。
事業譲渡、事業継承との違い
事業承継と似たような意味の語として「事業譲渡」という言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。
これは承継とは似て非なるものです。
事業承継は「これまで築いてきたものを、自分が選んだ後継者に全て託す」ことであり、その中には経営者の「理念」や「姿勢」といった目に見えないものも含まれます。
一方、事業譲渡にはそうしたものは含まれません。
あくまで経営権や資産を引き継ぎ、事業を継続していくだけです。
また、通例、会社自体は引き継ぎの対象にはならないため、譲渡後に会社が存続することもあれば、整理されてしまうこともあります。
ちなみに承継と同じ意味の語として「継承」がありますが、これは「権利や財産など実在するものを実際に受け継ぐ」ことで、やはり承継とは少々ニュアンスが異なります。
中小企業では深刻な問題に
本来、事業承継は、経営者にとって人生の集大成とでもいうべき「最後の大仕事」であり、自らの花道を飾るものとなるはずです。
ところが現実にはなかなかスムーズにいかないことも多く、とりわけ中小企業においては、昨今深刻な問題と化しています。
その最大の理由は「後継者不足」です。
一般に中小企業は創業者である社長が1人で会社を切り盛りしている場合が多く、社員もよくいえば「少数精鋭」です。
大企業のように後継者候補が豊富にそろっているわけではありません。
また、以前は息子が父親の後を継ぐというのが一般的でしたが、近年は「自分と同じ苦労はさせたくない」ということから身内に引き継ぐことを望まない経営者も増えています。
かといって、外部から適任者を探し出すのも簡単なことではありません。
後継者が見つからなければ、残る選択肢は「廃業」の一択になってしまいます。
実際、そうしたケースは増加傾向にあり、先述のとおり深刻な問題となっています。
準備は早いスタートが重要
自ら望んで自分の代で終わらせるという場合は別にして、自分が築いた会社や事業を今後も継続したい、誰かに受け継いでほしいと思うのであれば、まず「早い段階から動き出す」ということが何より重要です。
余裕をもって早めにスタートしておけば、後継者をじっくり時間をかけて探すことができます。
将来の後継者として若手社員に英才教育を施すというようなことも可能です。
事業承継の方法は?

実際に事業を承継する方法としては、どのような方法があるのでしょうか。ひとつずつ見ていきましょう。
後継者に引き継ぐ
引き継ぐ相手は主に経営者の家族や親族、もしくは社内の適任者です。
どうしても適任者が周りにいない場合は、稀に社外から登用することもあります。
親族内で承継する場合
実子が一般的ですが、配偶者や兄弟姉妹、場合によっては配偶者の兄弟姉妹が引き継ぐこともあります。
親族ならお互いに気心も知れていますので、承継も比較的スムーズに進むことが期待できます。
もともと「いずれ息子が後を継ぐ」というようなコンセンサスができ上がっている場合も多いため、社内でもすんなり受け入れられやすいという面もあります。
一方、親族といっても、社員としての経験をせずにいきなり社長に就任するといった場合は要注意です。
経験のなさや唐突感から、周囲から不安や不満が生まれる可能性もあります。
さらに親族内でコンセンサスがとれていなければ、承継をめぐって身内同士のトラブルに発展する恐れもあるでしょう。
近年では、子どもたちがそれぞれ自分で選んだ道に進んでいったり、経営者のほうが親族に承継することを望まなかったりといったケースが増えているため、家族による承継は減少傾向にあります。
31~35年前までは実に子ども・親族の承継が98%を占めていましたが、その数は少しずつ減っており、現在では69%ほどです。
参考:事業承継の実態に関するアンケート調査報告書ほか|東京商工会議所
社内で承継する場合
一方で役員や従業員、社外からの親族外登用は少しずつ増える傾向にあります。
実力のある有望な若手や自分の片腕とでもいうべき信頼できる社員を後継者に据えるケースです。
気心も知れており、なおかつ事業や社内の事情にも精通しているため、後継者としては申し分ありません。
ただしこの場合も、古参の社員たちを飛び越えた大抜てき人事だったりすると、社内でコンセンサスが得られず、反発を招くこともあります。
また、社員の金銭的な理由などから、会社の株を取得できない場合もあるでしょう。
この場合は引退したはずの元経営者が変わらず会社の株主ということになってしまい、好ましい状況とはいえません。
M&Aを行う
「M&A」は「Mergers and Acquisitions」の略です。直訳すると「合併と買収」という意味です。
その名のとおり、合併や買収を行うことによって自社の規模を拡大していく経営手法のことですが、これを活用して他社に事業を承継する方法もあります。
もちろん他社を買収するわけではなく、他社に買収を持ち掛け、交渉していくことになります。
実績や知名度のある会社なら、逆に他社から話を持ち掛けられることがあるかもしれません。
買収にはいくつか方法がありますが、中小企業では「株式譲渡」がよく行われます。
この場合、経営者には個人として売却益が得られるというメリットが生まれます。
また会社にとっても、自社にはない技術やノウハウを取り入れることもできるため、事業の発展につながることも期待できるでしょう。
身近に「これは」と思える後継者がいない場合には、大変有用な方法になるはずです。
M&Aなら仲介業者の利用がおすすめ
ただし、よほど旧知の間柄ということでもなければ、経営者が個人で他社相手にM&Aを持ち掛けるのは困難です。
実際に行うとなった場合には、国の「事業引継ぎ支援センター」などに依頼するのが通例でしょう。
民間の場合、最近はインターネットで利用できるマッチングサイトや仲介サービスが人気を集めています。
株式を上場する
「株を上場することが、なぜ事業の承継になるのか」と疑問に思われる方もいるでしょう。
もちろん上場が直接事業の承継になるわけではありません。上場させるとなれば、当然「創業者の個人商店」的な会社のままではいられません。
役員などもきちんと設ける必要が出てきます。
そうした流れの中で必然的に周囲も認めるリーダー(後継者)候補が生まれ、結果として事業承継につながることが期待できるということです。
実際に上場企業となれば、ステータスが上がり人材も集まりやすくなるため、後継者選択の幅も広がります。
ただし株式の上場は、「希望すれば、いつでも誰でもできる」というような簡単なものではありません。
上場する取引所によって必要な条件が明確に規定されており、それを満たしたうえで、なおかつ審査を受け、承認してもらう必要があります。
ハードルは非常に高く、残念ながらこの方法を活用できるのは一定の規模以上の企業に限られてしまうというのが実情です。
信託制度を利用する
信託制度とは「信じて託す」という名前のとおり、「信頼のおける個人や企業に、自己の財産の管理や運用を委託する」ことです。
よく知られているところとして「投資信託」があります。
具体的には、財産をもっている人(委託者)が信頼できる人(受託者)にその管理や運用を依頼します。
そして運用によって得られた利益などを、受託者が責任をもって委託者が指定した人(受益者)に渡します。
受益者は委託者本人でも、別の第三者でも構いません。
この制度を事業承継に活用する方法もあります。
つまり経営者が会社の株式等を直接後継者に引き継ぐのではなく、受託者を経由して間接的に利益が得られるようにするということです。
譲渡を伴わないため手続きも容易です。先述したように、金銭的な問題で後継者が自社株を取得できないというような場合にも解決策のひとつになりえます。
株式を一定数以上保有すると経営権が発生するため、希望する後継者に確実に譲れるのもメリットです。
また受益者の次の代の人も受益者とできる制度もあるため、例えば息子に加えて孫も後継者に据えておくといったことも可能です。
ただ正直なところ、この方法は一般的にはまだあまり知られておらず、後継者も含めて周囲の理解を得るのは少々難しいかもしれません。
まとめ
いずれの方法で行うにしても、承継は数日で完了するようなものではありません。
会社を引き継ぎ、経営が安定し軌道に乗るまでには、一定の時間がかかると考えておく必要があります。
事業承継をする予定なら、やはりできるだけ早くスタートを切ることが重要です。
またこうした観点から見ていくと、M&Aを活用する方法が優位といえるかもしれません。
その場合はM&Aのマッチングサイトの利用をおすすめします。
例えばウィルゲートではWeb・IT業界を中心とした事業や株式の譲渡・譲受のマッチングをワンストップで行っています。
幅広い選択肢から最善の決定ができるように支援してくれる有益なサービスです。
 sirasaka / 編集長
sirasaka / 編集長
弊社マーケットエンタープライズが運営する総合買取サービス「高く売れるドットコム」にて査定業務や出張買取などに携わり、現場で培ったリアルな知見を活かし「満足できる買取体験」を提供すべく買取メディアの運用も行っています。 利用者様の買取にまつわる疑問を解決できる有益な発信のため、日々精進してまいります! リユース営業士資格保有(日本リユース業協会より授与)
関連キーワード