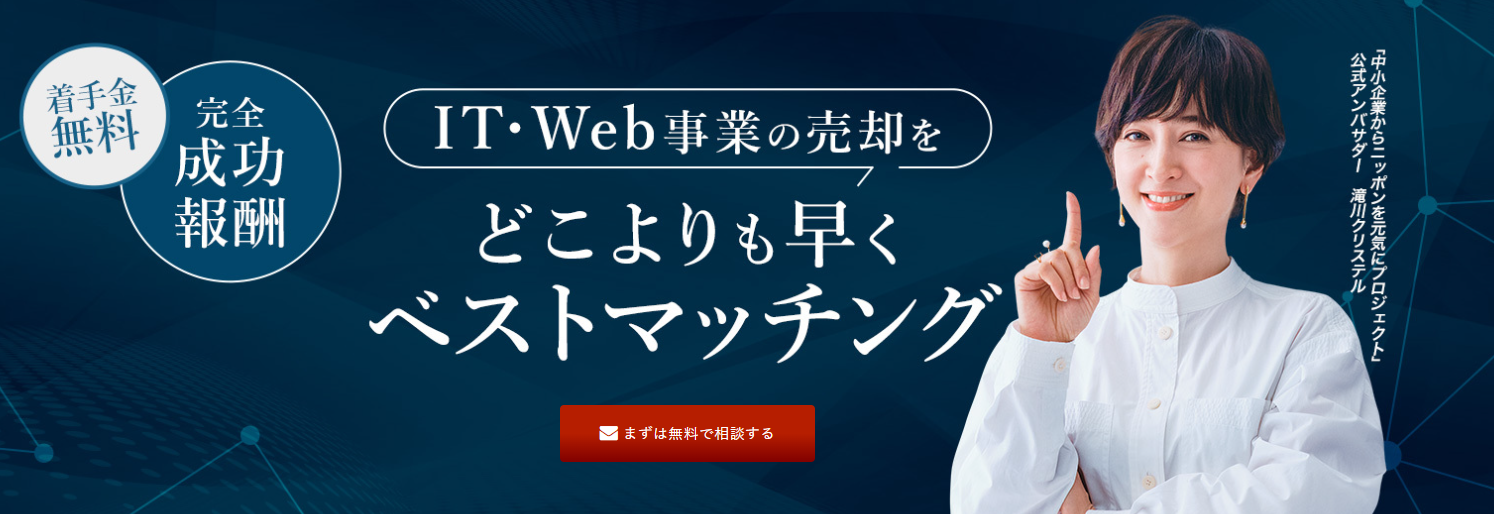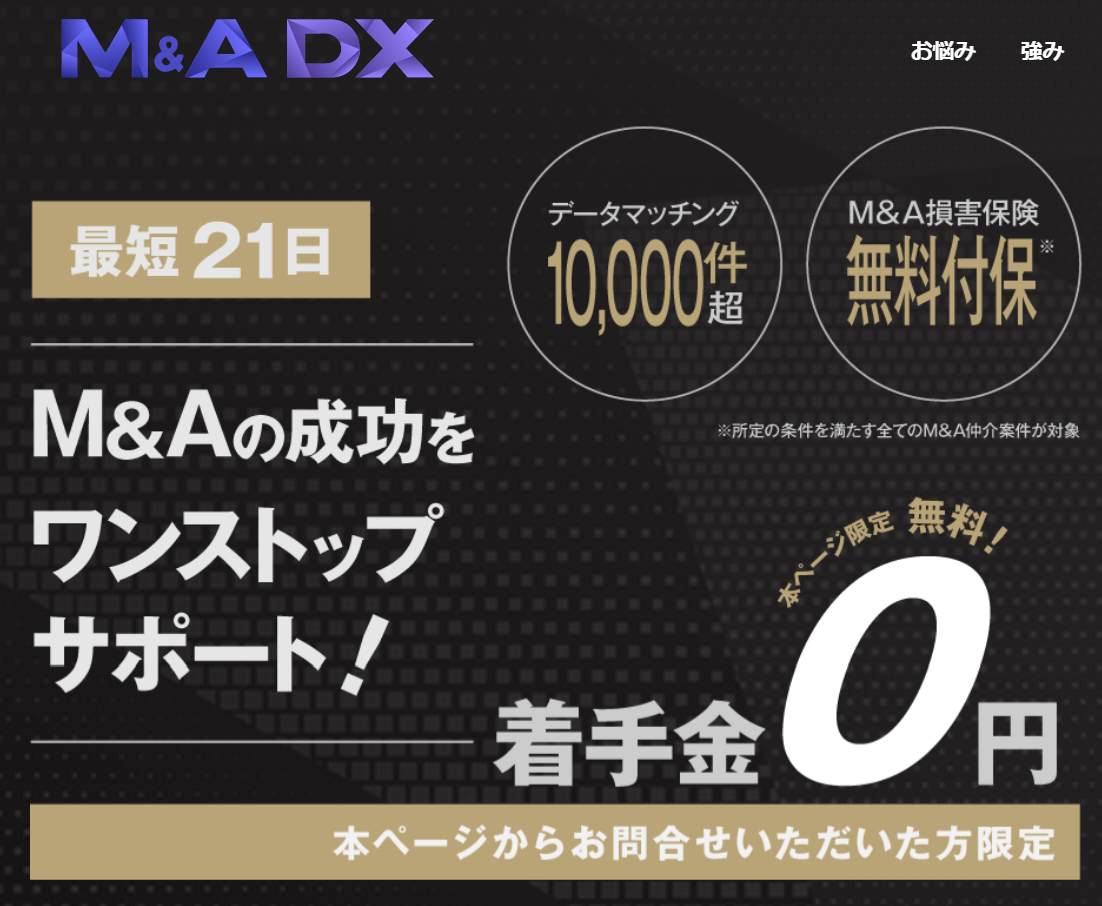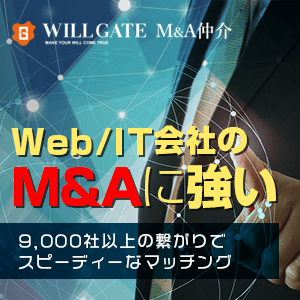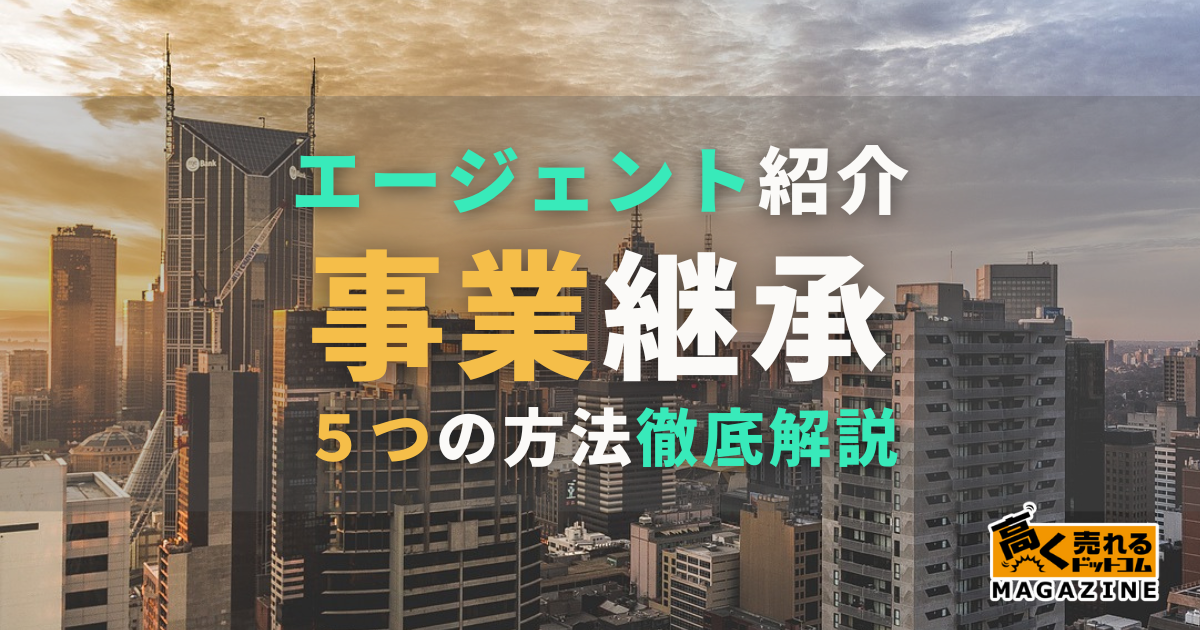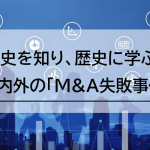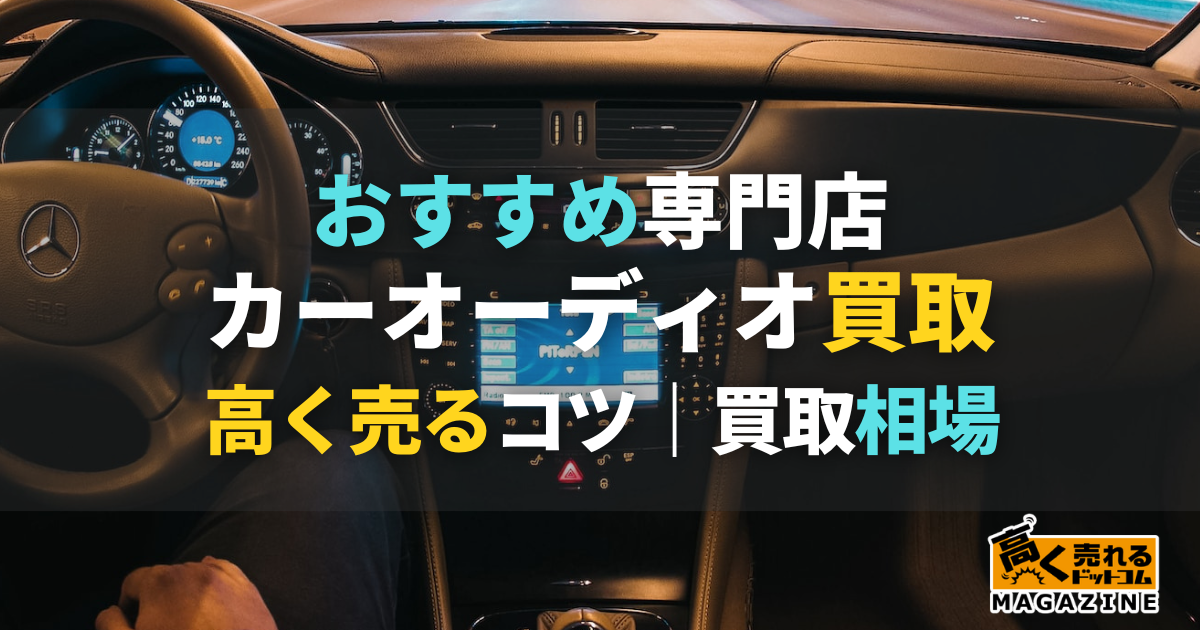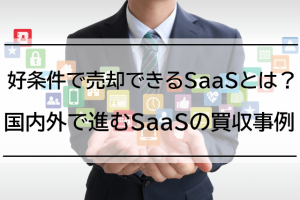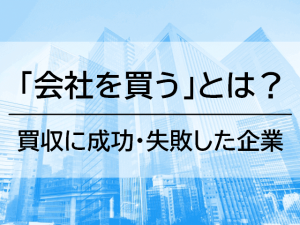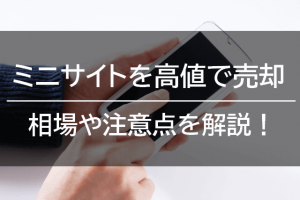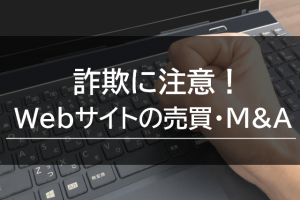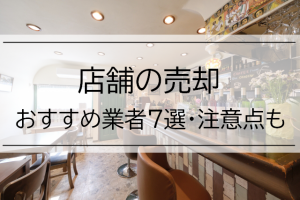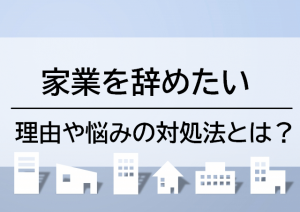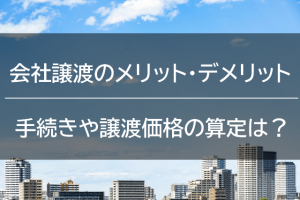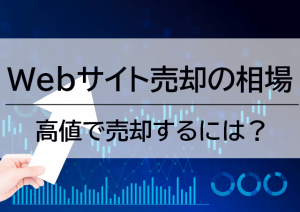- サイト売買・M&A
事業売却とは?メリット・税金・手続きなど解説

※当記事はアフィリエイト広告を含みます。
※「高く売れるドットコム」「おいくら」は弊社マーケットエンタープライズが運営するサービスです。
これから事業売却をしたいと考えている人のなかには、どのように着手すればよいのかわからない人もいるでしょう。
事業売却は事業のみを売却できることから、中小企業や個人事業主を中心に広く活用されています。
ここでは、事業売却の定義やメリット・デメリット、株式譲渡との違いや基本的な手続きの流れなどについて、わかりやすく解説します。
サイト・事業売却をお考えの方へ
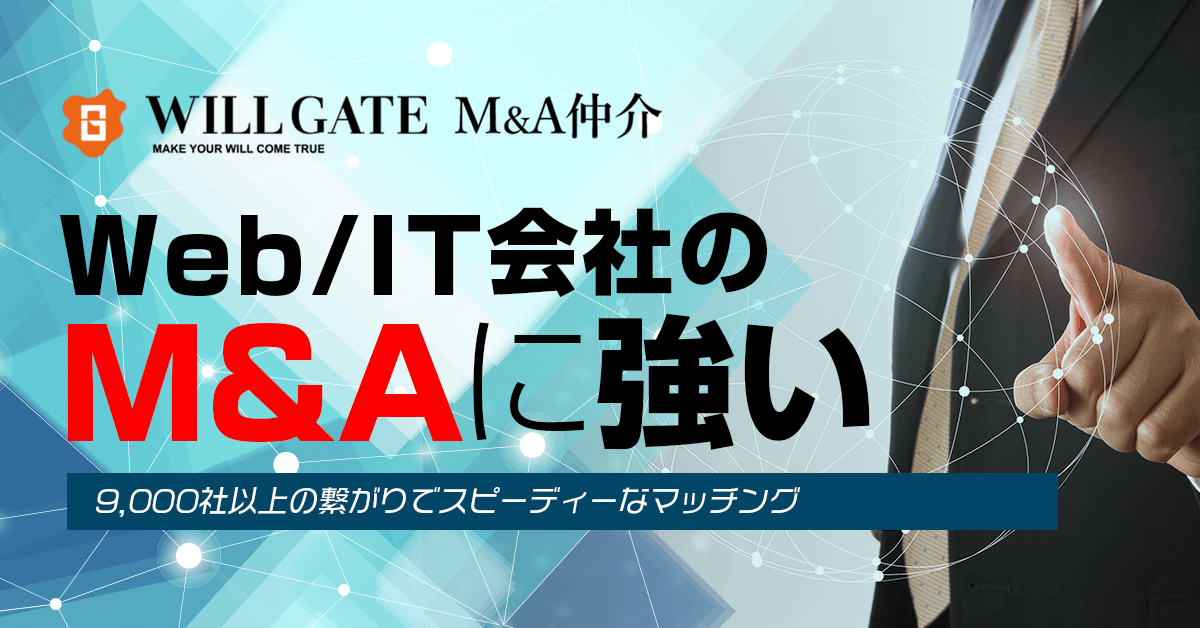
取引実績250社以上!
IT・Web事業領域の売却ならウィルゲートM&A
※相場情報は実際の買取価格と異なる可能性がございます。
事業売却おすすめエージェント3選
Willgate M&A
「Willgate M&A」はIT・Web事業のM&Aに精通している業者です。
Willgate M&Aの大きな魅力は買い手企業の数です。開始から僅か3年で買い手企業の掲載数が1,700社を超え、売り手と買い手のマッチングが叶いやすいサービスとなっています。
成約実績も44件と豊富に持っており、評価額40億円越えの成約実績も持っています。
数多くの成約実績を持っている理由として、有名企業の経営者との繋がりがあります。Willgate M&Aは17年に渡り、Webマーケティングに注力している7,400以上の企業の支援を行ってきました。
これらの取引実績や独自のネットワークから、現在では上場企業を含む9,100社以上との繋がりを持っています。これらの企業と密な連携を図る事でスピーディかつ適切なマッチングを可能にしています。
また、Willgate M&A自身も2度の事業譲渡、4度の事業譲受の経験が有るからこそ、経営者の気持ちを理解し、丁寧なサービスの提供を実現しています。
「IPOではなくバイアウトを検討している」「一部事業を清算し、新規事業への投資拡大をしたい」「大企業と組んで事業を拡大していきたい」などの悩みをお抱えの企業・事業主におすすめのサービスです
M&A DX
出典:M&A DX公式サイト
「M&A DX」は10,000件を超えるデータマッチングの実績を誇るサービスです。
M&A DXの魅力は豊富な種類のサービスです。通常のM&A会社は5つ程度のサービスしか行っていません。しかし、M&A DXは20ものサービスを提供しており、事業継承・事業再生等のお悩みをまるっと解決します。
また、東京・大阪・名古屋・福岡に拠点を持ち、全国の経営者に寄り添ったサービスを実現しています。
さらに、公認会計士・弁護士・税理士などのM&A専門家率は5割を超え、これらのプロフェッショナルや、全国の金融機関・士業と連携することで M&Aおよび事業継承を最適化します。
M&A DX公式ページからのお問い合わせで着手金が無料でサービスをご利用いただけます。
また、M&A損害保険・相談などが全て無料で、M&Aの成功をワンストップサポートします。
相談だけでも大歓迎です。ぜひ、ご利用ください。
M&Aクラウド

出典:M&Aクラウド公式サイト
「M&Aクラウド」は買い手の責任者とすぐに会うことができるプラットフォームを提供している業者です。
IT上場企業の20%以上を買い手として掲載中です。大企業だけでなく、多くのベンチャー企業や中堅企業の掲載実績も豊富に持っているサービスです。
この他にも、DX(デジタル・トランスフォーメーション)に関心のある非上場企業も多く掲載しています。
「自社だけでは事業を次のステージに進めるのが難しい」
「会社や事業の売却方法が分からない」
などの悩みをお持ちの方におすすめのサービスです。
M&Aクラウドは買い手のM&Aニーズ・買収実績・独占インタビューなどを公開しており、M&A成立後のミスマッチが起こりにくいシステムになっています。
また、仲介業者が間に入ることが無いため、買い手と直接取引を行えます。マッチングから面談までの平均時間は1週間程度と、スピーディーに交渉を始められるのも大きな魅力です。
さらに、着手金や成約手数料を初め、プロのアドバイザーへの相談なども全て完全無料でご利用いただけます。
完全無料で利用できるプロのアドバイザーへの無料相談だけでもお試しください。
事業売却とは?

事業売却とは、会社や個人が行っている事業の一部や全てを他の会社や個人に譲渡することです。
これは、M&A(企業の買収・合併)の手法の一つとして用いられています。
事業売却では、有形資産や無形資産など事業に関わる幅広い対象が譲渡の対象です。
有形資産では、土地をはじめ工場や店舗、機械などが譲渡できます。
さらに、無形資産では、知的財産やブランド、顧客リストや契約まで譲渡の対象として含まれます。
事業を売却するときの細かい内容は、当事者間で「事業譲渡契約書(または営業譲渡契約書)」にて取り決めます。
事業売却時のトラブルを防止するためにも、事業譲渡契約書は必ず事前に取り交わすようにしましょう。
事業売却に関しては、会社については会社法、個人については商法に規定が置かれています。
会社法が適用される事業売却については「事業譲渡」、商法が適用される個人事業主などが行う事業売却においては「営業譲渡」が適用されます。
2006年の会社法・商法が改正される前は、会社が行う事業売却についても「営業譲渡」と呼ばれていました。
「株式譲渡」との違い
中小企業のМ&Aにおいては、事業売却とともに株式譲渡が多く行われています。
株式譲渡とは、売り手企業の株主が保有する株式を買い手に譲渡し、会社の経営権を承継させることです。
株式譲渡は株主の全てや一部の株主構成が変更されるだけで、会社の組織や事業はそのまま引き継がれます。
会社の資産や取引先との契約、従業員との雇用関係や不動産の所有権などは、売り手側に存続するのが原則です。
株式譲渡の対価の支払いは、譲渡した株主に対して行われます。
株式譲渡のメリットとして、手続きが簡素でスピーディな対応が可能であることが挙げられます。
早急に現金化したい場合などに、株式譲渡が行われるケースが多いことが特徴です。
「事業売却」のメリット

事業売却には、売り手側にも買い手側にもメリットがあります。
この段落では、事業売却のメリットについて解説します。
売り手側のメリット1.売却資金を得ることができる
売却の対価として、売却資金を得ることができます。
事業売却で得られた売却資金を借入金の返済や運転資金に充てたり、残った事業や新規事業へ投資できたりします。
売却後に廃業を予定している場合には、従業員・役員に対する退職金や退去・処分などの廃業費用に充てることで、経営者の生活の安定を図ることも可能です。
また、ベンチャー企業が事業売却を活用し、資金調達や創業者利潤を獲得しているケースもあります。
売り手側のメリット2.一部の事業のみ売却できる
事業売却は、一部の事業のみを譲渡することが可能です。
そのため、経営不振であっても採算事業を残し、不採算事業のみを売却できます。
それによって、経営が効率化され会社の再生を図れます。
売り手側のメリット3.事業の後継者を確保できる
中小企業や個人事業主の後継者のほとんどは、子息などの親族がほとんどでした。
しかし、少子化の影響もあり多くの経営者に後継者がおらず、経営が好調であっても会社の清算や廃業を迫られるケースも少なくありません。
そのような場合でも、事業売却をすることで第三者へ事業を承継できます。
売り手側のメリット4.特定の資産や従業員を残すことができる
事業売却では、譲渡する内容について当事者間で協議しながら決定します。
そのため、資産や従業員を選定し残すことが可能です。
事業にとって必要となる資産や従業員が残ることで、複雑化した事業を整理したり新しい事業へ進出したりもできます。
売り手側のメリット5.債権者への通知が不要
事業売却をする場合には、債権者への通知は必要がありません。
債権者からの問い合わせや手続きに時間を割くことなく、事業売却の手続きを進められます。
ただし、売り手側と買い手側の企業が支払い債務を負う必要があります。
買い手側のメリット1.必要な資産や事業だけを譲り受けることができる
株式譲渡や会社合併では、必要ではない不採算事業などを買い手側が引き継ぐ必要があります。
しかし、事業売却では事業の拡大や新規事業に必要な資産や従業員のみを譲り受けることが可能です。
買い手側のメリット2.簿外債務のリスクを負わない
事業売却では、契約する際に引き継ぐべき債務が確定しています。
買い手側にとっては、簿外債務のリスクを負う必要がなく安心して事業売却が行えるでしょう。
買い手側のメリット3.低コストで事業拡大・新規参入できる
既存の事業を引き継ぐことで、低コストで事業規模の拡大を図ることが可能です。
さらに、売り手から引き継いだ事業のノウハウを活かし、新規事業に進出することもできます。
買い手側のメリット4.のれん代を償却できる
事業を買い取る場合は事業の現在価値に加え、その事業が将来的に生み出すと予測される価値を「のれん代」として上乗せします。
のれん代は最長20年間で減価償却し、節税できるのがメリットです。
のれん代の算定は複雑であるため、専門家に依頼するケースが多いでしょう。
「事業売却」のデメリット
事業売却をするときには、売り手側も買い手側もデメリットを押さえておく必要があります。
リスクを負わないためにも、事業売却におけるデメリットを踏まえ検討しましょう。
売り手側のデメリット1.株主総会の特別決議承認が必要
会社が事業売却を行う場合、株主総会での特別決議で承認を得ることが会社法467条で定められています。
特別決議の承認には、議決権を持つ株主が過半数出席し、議決権の3分の2以上の賛成が必要です。
株式が多くの株主に分散している場合には、賛同を得るまでに長い期間を要するケースもあります。
売り手側のデメリット2.債務が残る場合がある
事業売却では、債務の引継ぎを売り手側から拒否される場合もあります。
相当額の売却資金を得られるとしても、事業売却後のキャッシュフローについて慎重に検討することが大切です。
債務が引き継がれることになっても、債権者との交渉や名義・保証人の変更などの手続きに時間がかかる恐れもあります。
売り手側のデメリット3.売却益には税金がかかる
事業売却により企業が売却資金を得た場合には法人税がかかり、個人の場合には所得税の課税対象となります。
消費税を負担するのは買い手であるため、売り手側が徴収してから税務署へ納めましょう。
買い手側のデメリット1.事業買取資金が必要
事業を買い取るためには、元手となる資金が必要です。
資金がない場合には、事業計画を立て金融機関などから資金を調達するなどの方法があります。
買い手側のデメリット2.各種手続きが必要
М&Aを行う際には、さまざまな移転手続きや契約変更を行います。
例えば、不動産の所有権移転を申請する手続きが必要です。
取引先を引き継いだ場合には、新たな契約の締結や取引条件の見直しを行うようにしましょう。
買い手側のデメリット3.許認可の新たな取得が必要
事業に必要な許認可は、事業売却では引き継ぐことができません。
買い手側が許認可を得ていない事業については、新たに許認可を取得することが必要です。
買い手側にとって許認可を得ることは煩雑な業務であるため、事業売却着手への大きな壁となっているケースも少なくありません。
買い手側のデメリット4.従業員の引継ぎ
従業員を引き継ぐ場合には、新たな雇用契約の締結や社会保険などへの加入手続きも必要です。
事業に必要な従業員であっても、買い手側へ転出することを拒む場合もあります。
従業員を引き継いだとしても、新たな環境や待遇への不満により早期退職の原因となる恐れもあります。
買い手側のデメリット5.消費税・不動産取得税を支払う義務がある
買取資産の中に、機械や車両などの課税資産が含まれていれば、消費税が課税されます。
土地や建物などの不動産を取得した場合には、不動産取得税が課税され、所有権移転登記する際には登録免許税が必要です。
「事業売却」の手続きの流れ

事業売却をする際には、手続きの流れをあらかじめ理解しておくことでスムーズに取引を行えます。
この段落では、会社が事業売却する際の手続きの流れを紹介します。
1.事業売却のシミュレーションを行う
事業売却する際には事業ごとの強みや弱みを分析し、事業売却額の算定を行いましょう。
事業売却後の収益や資金繰りのシミュレーションを行うことは、事業売却をするうえで重要視するべきポイントです。
2.売却先の決定
次に、M&A仲介会社のような専門家から意見を仰ぎ、売却先候補を選出し交渉を開始します。
売却先が決定した後に、譲渡日や譲渡内容など、事業売却についての大まかな条件について協議し「事業譲渡基本合意書」を締結しましょう。
3.デューデリジェンス(適正評価手続き)
買い手側は、売り手側の財務や法務や人事、取引関係や設備や状況などについて幅広い観点から調査します。
この買い手側の調査のことを「デューデリジェンス」と呼びます。
デューデリジェンスは事業売却時のリスクを把握するとともに、事業の将来の収益予測する大切なステップです。
4.取締役会の承認
取締役会設置会社では、事業売却を行う際に取締役会で過半数の承認を得ることが必要です。
その後、提示された売却価額や譲渡する資産、従業員の引継ぎや諸条件について当事者間で協議します。
条件について双方が合意した場合には「事業譲渡契約書」を締結します
5.株主総会の特別決議
株主総会の特別決議による承認が必要な事業売却の場合、譲渡契約の効力発生日の前日までに株主総会を開催するようにしましょう。
そのうえで、出席株主の議決権の3分の2以上の承認を得る必要があります。
6.許認可などの手続き
事業譲渡契約の効力発生日までに、許認可や名義変更など必要な手続きや取引先などとの契約締結を進めましょう。
なかには継承できない許認可もあるため、あらかじめリサーチすることが重要です。
7.クロージング
最後に、売り手側と買い手側が協力し、統合作業を行いましょう。
統合作業とは、売り手側のシステムを買い手側のシステムに統合させる作業を指します。
事業売却に必要な手続きが完了し、買い手側から売却資金が支払われることでクロージングとなります。
まとめ
事業売却は、買い手側にも売り手側にもメリットがある経営施策です。
しかし、事業売却する前には、デメリットや予想されるリスクなどを把握したうえで手続きを進める必要があります。
事業売却を進めるにあたって、財務や法務などの専門的な知識や高度な交渉力が必要不可欠です。
事業売却を成功させるためには、M&A仲介会社などの専門家からのアドバイスを活用しましょう。
 sirasaka / 編集長
sirasaka / 編集長
弊社マーケットエンタープライズが運営する総合買取サービス「高く売れるドットコム」にて査定業務や出張買取などに携わり、現場で培ったリアルな知見を活かし「満足できる買取体験」を提供すべく買取メディアの運用も行っています。 利用者様の買取にまつわる疑問を解決できる有益な発信のため、日々精進してまいります! リユース営業士資格保有(日本リユース業協会より授与)
関連キーワード