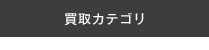掛軸買取 - 骨董・古美術を高価買取

電話で買取価格を調べる
[ 年末年始除く 9:15~21:00 ]
掛軸(掛け軸)の買取なら、業界最大級の買取サービス「高く売れるドットコム」!
利用者数150万人突破の買取サービスだから、豊富な買取実績をもとに掛軸を高く買い取ります。
古い掛軸や、作家名のわからない掛軸もお買取が可能です。買取のご相談や無料査定のお申し込みは、お電話とWebから受け付け中です。
掛軸(掛け軸)買取の流れ
- 査定申し込み
「買取価格を調べる」ボタンから、買取査定を申し込みます。売るかどうか決まっていない場合や、買取価格を知りたいだけでも問題ありません。査定は完全無料となっており、無料の出張査定も行っています。 - 買取方法の決定
専門の担当者が査定を行い、買取価格をご連絡します。買取価格を確認いただいたら、出張・宅配・店頭持ち込みから最適な買取方法をご案内します。買取は日本全国に対応しており、近くに店舗がない場合でもお買取可能です。 - お支払い
選んだ買取方法にしたがって、掛軸の引き渡しとお支払いをします。出張買取・店頭買取の場合は現金手渡し、宅配買取の場合は銀行口座にお振り込みです。掛軸以外にも巻物の買取といった骨董品の買取全般を行なっております。
電話で買取価格を調べる
[ 年末年始除く 9:15~21:00 ]
掛軸(掛け軸)の査定ポイント
掛軸の作者
掛軸の査定ポイント1つ目は、掛軸の作者が誰かです。
掛軸は作品自体の美しさも大事ですが、それよりも誰が作った作品なのかで大きく価値が変わります。有名な作者の掛軸は中古市場でも高く評価され、買取価格が高くなる傾向にあります。掛軸には、作者の署名や印章と呼ばれる印が押されているため、ここから作者が特定できます。
落款の有無
掛軸の査定ポイント2つ目は、落款(らっかん)があるかどうかです。落款とは、掛軸の隅についている印鑑や判子のことです。絵師本人が描いたことを証明するサインのようなもので、画家としての名前である「雅号」を判子にしています。
生涯で雅号を何度も変えている絵師もおり、年代識別に落款が用いられることもあります。落款は掛軸作家の特定に役立つだけでなく、本物かどうかの真贋判定においても重要です。落款のある掛軸は作家本人のものである可能性が高く、高価買取が期待できます。
掛軸の状態
掛軸の査定ポイント3つ目は、掛軸の状態です。
古い掛軸や保存状態が悪い掛軸の場合、劣化、変色、シミ、裂けなどのダメージが見られる場合があります。掛軸は居間などに飾って鑑賞する美術品のため、状態が悪い掛軸は買取価格も下がってしまいます。そのため、作者のみならず掛軸自体の保存状態も査定価格に影響するポイントです。
掛軸(掛け軸)の有名作家
掛軸の有名作家一覧
- 横山大観
- 棟方志功
- 円山応挙
- 尾形光琳
- 雪舟
- 川合玉堂
- 上村松園
- 竹内栖鳳
- 速水御舟
- 川端龍子
- 小林古径
- 酒井抱一
- 菱田春草
- 宮本武蔵
- 狩野探幽
雪舟
雪舟は(せっしゅう)室町時代に活躍した水墨画の名手であり、画僧としても知られています。水墨画は墨の濃淡を使って描かれる絵で、中国から日本に伝わりました。雪舟の作品は国宝とされ、その多くは60歳半ば以降に描かれています。
雪舟は若い頃から絵の才能を発揮し、京都で画家としての名声を築きました。中国への留学で技術に磨きをかけ、帰国後は日本の風景や名所を描いて高く評価されています。雪舟は80代半ばまで活動し、生涯を通じて創作意欲が衰えることはありませんでした。
雪舟の代表的な作品は、『秋冬山水図』と『天橋立図』です。『秋冬山水図』は2幅から成り、それぞれ異なる季節の景色を描いています。右幅では、手前から奥へと岩組が交互に配されて整理された構成を取り、左幅では大胆に切り取った懸崖の垂直線を中心に景物が複雑に重ね合わされています。どちらも国宝に認定されている、水墨画の傑作です。
尾形光琳
尾形光琳(おがたこうりん)は、江戸時代中期に活躍した琳派の代表的な画家です。伝統的な大和絵に、斬新で大胆な構図や色彩を取り入れた画風を特徴としています。
尾形光琳は金箔をふんだんに使った屏風絵で知られ、後の日本文化に大きな影響を与えました。生まれは京都の呉服商の次男として裕福な家庭に生まれ、幼い頃から文化芸術に親しんで育ちました。
尾形光琳の代表作『燕子花図屏風』は、緑青と群青の濃淡で描かれたカキツバタの群生が鮮烈に表現されています。1000枚以上の金箔が使用されており、金箔の重ね方にも工夫が凝らされた作品です。
横山大観
横山大観(よこやまたいかん)は近代日本画の巨匠であり、特に富士山を題材にした作品で知られています。横山大観は岡倉天心の指導を受け、伝統的な日本画の枠を超える新しいスタイルを模索しました。
横山大観は富士山を四季折々や時間帯ごとに描き分け、その作品数は1500点以上に及びます。代表作の『乾坤輝く』は富士山の描写と、自然の壮大さを表現した力強い筆致が特徴です。絵画の中心にそびえ立つ富士山は、乾と坤、つまり天と地を象徴しており、その輝きが全体を包み込むように表現されています。
晩年には新たな表現を模索し、日本画の発展に大きく貢献しました。横山大観の死後も、その遺産は多くの人々に影響を与え続けています。
棟方志功
棟方志功(むなかたしこう)は、版画家として有名な作家です。棟方志功は1903年に青森市で生まれ、独学で油彩画を学びました。初期の作品は後期印象派の影響が見られますが、後に独自の表現スタイルを確立しています。
棟方志功の作品は「板画」と呼ばれ、その独創性や大衆的な人気が高く評価されました。木版画が有名ですが、墨を使った肉筆画の掛軸や屏風なども残っています。
棟方志功は民芸運動の作家たちと交流し、日本の伝統文化や仏教にも関心を寄せました。戦時中は東京にとどまりましたが、終戦後は国際的な評価を受け、渡米して個展を開催しました。
円山応挙
円山応挙(まるやまおうきょ)は、18世紀後半の江戸時代後期に活躍した絵師です。特筆すべきは、空間デザインにおける卓越した才能です。
円山応挙は、「応挙寺」として知られる兵庫県の香住にある大乗寺の襖絵を手がけました。この寺は、客殿全体が一種の立体曼荼羅として構想され、四隅の部屋の襖絵は十一面観音菩薩をお守りする四天王を象徴しています。このように、寺院全体が宗教的な体験と結びついた空間デザインは、円山応挙の独創性と才能を示すものです。
円山応挙の代表作としては、『幽霊図』や『雪松図屏風』が挙げられます。『幽霊図』は、円山応挙が描いた幽霊のイメージを決定づけた作品として知られています。幽霊が腰から下がスウッと消えているように描かれており、その儚さや不思議な雰囲気が表現されています。
掛軸(掛け軸)買取のよくある質問
掛軸の買取相場はどれくらい?
掛軸の買取相場は、0円〜50万円ほどとかなり幅広いです。無名の作者の掛軸は買取を行なっていない会社も多く、買取自体が難しい可能性が高いです。一方、著名な画家の掛軸は中古市場で100万円以上で取引されることもあり、数十万円の買取価格がつく場合もあります。
価値ある掛軸の見分け方は?
価値ある掛軸の見分け方として最もわかりやすいのは、作家名です。掛軸自体に作家の落款や印章がある他、「共箱」と呼ばれる作者本人が署名捺印した箱からも確認できます。これらを元に、有名な作者なのかどうかを調べるのがわかりやすい方法です。ただし、精巧に作られた贋作の可能性もあるため、最終的には専門家に鑑定してもらう方法をおすすめします。
掛軸の有名な作家は?
掛軸の有名な作家としては、伊藤若冲や与謝蕪村、横山大観などが挙げられます。掛軸の中にも風景画や人物画、花鳥画など様々な種類があり、それぞれの分野に有名な画家がいます。
掛軸はなぜ高いの?
掛軸は全て高いのではなく、掛軸の中にも高いものと安いものとがあります。高い掛軸は、有名な絵師の作品だからこそ高いのです。有名作家の掛軸は市場に流通している数が限られている上、欲しがる方も多くいます。そのため、高値で取引されているのです。