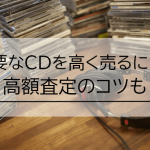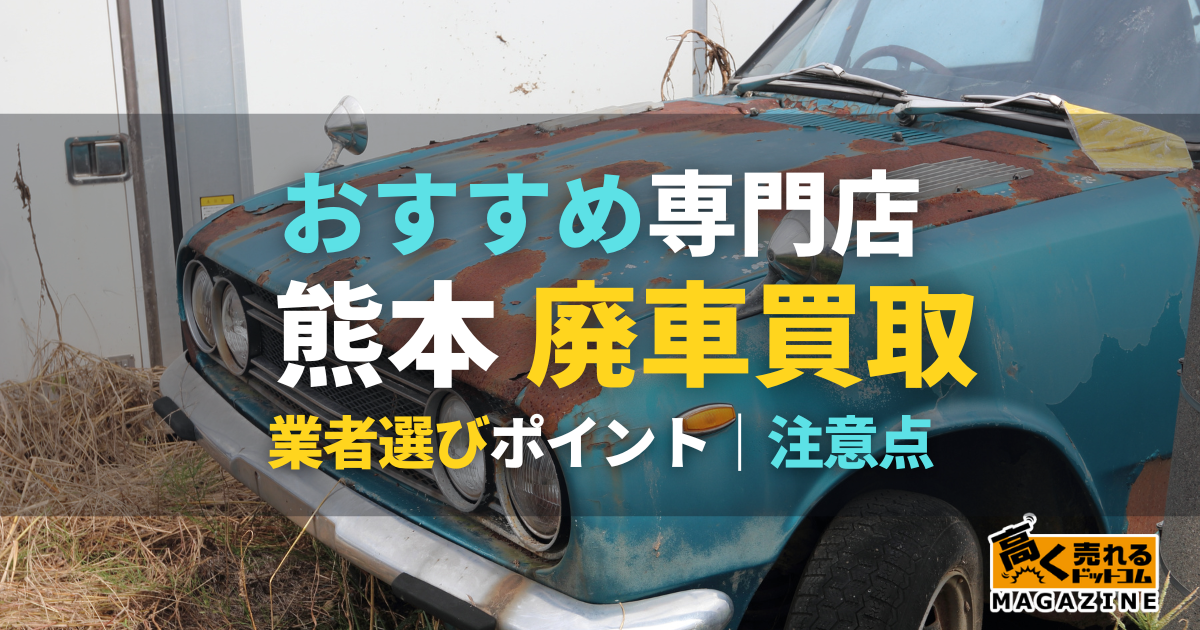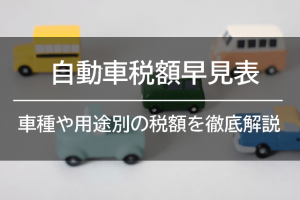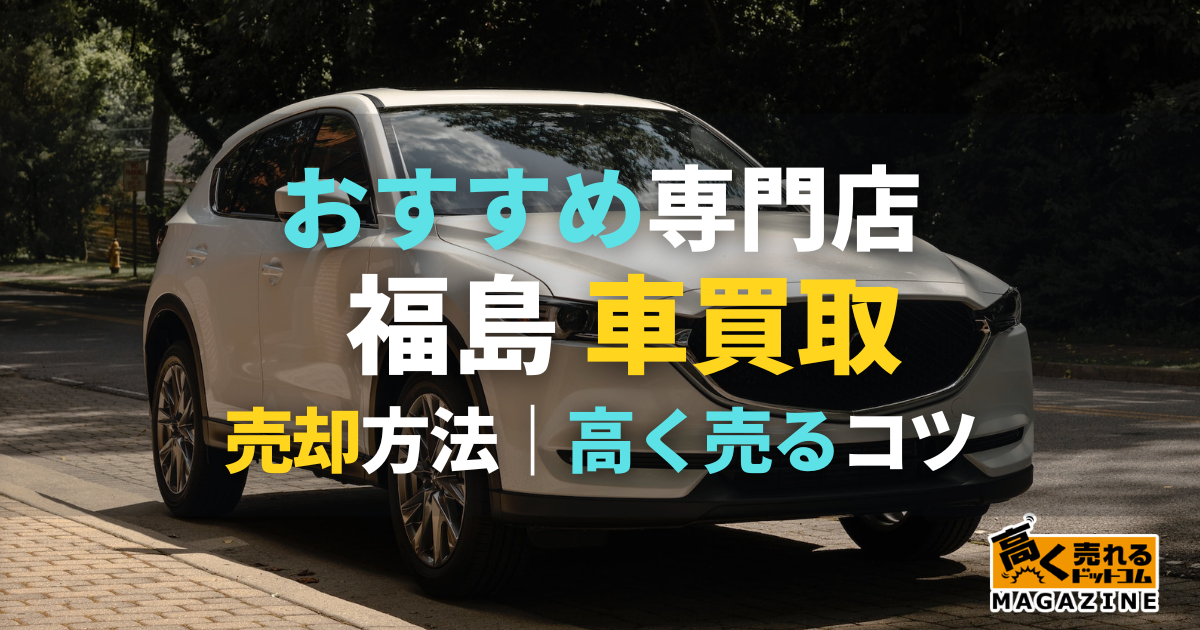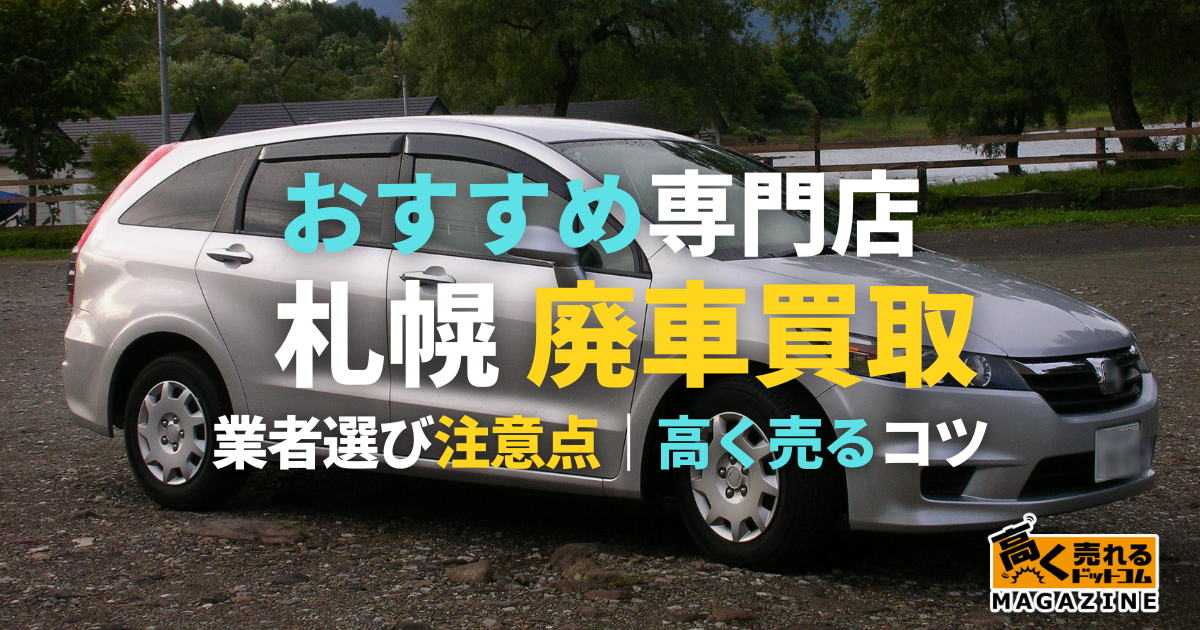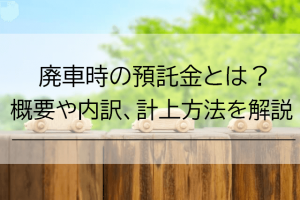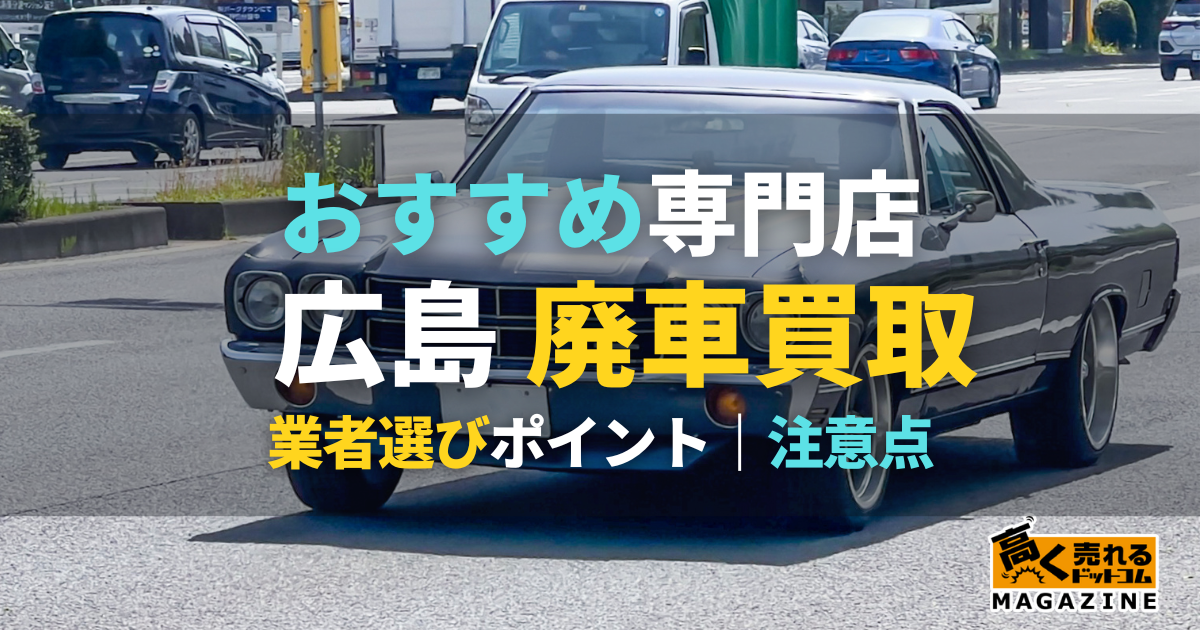- 車買取おすすめ
車両売却を考え中の方必見!仕訳方を1つに絞る方法
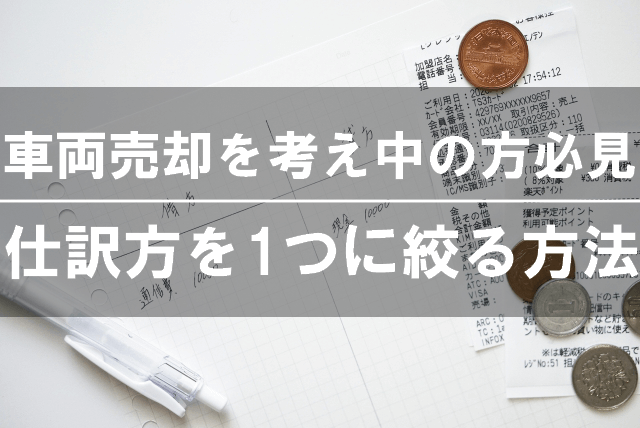
※当記事はアフィリエイト広告を含みます。
※「高く売れるドットコム」「おいくら」は弊社マーケットエンタープライズが運営するサービスです。
経費で購入した車両を売却するなら、その売却損益額も帳簿へ記入しなくてはなりません。その際必要なのは、適切な仕訳方を選ぶことです。
仕訳方を決定するのは、「減価償却が直接法か間接法か」「税込か税抜か」「売却主が法人か個人事業主か」という3要因です。つまりこの3つを整理することで、仕訳方は明確に定まるのです。
この記事では、上記3要因を順番に解説し、仕訳方をすっきりとまとめます。
目次
※買取相場は執筆時点で取得した情報となりますので、実際の買取価格と異なる可能性がございます。
仕訳を決める3要因
車両売却の際の仕訳を決めるのは、次の3つの要因です。
- 減価償却が、直接法か間接法か
- 税抜経理か税込経理か
- 法人か個人事業主か
この3つの要因が組み合わさることで、合計8パターンの仕訳方が生じます。車両売却の際の仕訳方は、この8パターンの内の1つに必ず定まります。
以下より、各要因に焦点を定めながら、仕訳方の仕組みを解説します。
要因1:減価償却
まずは、「減価償却」から解説します。経費購入した車両など、時間経過によってその価値が減少していく固定資産を「減価償却資産」と呼びます。
減価償却資産の購入金は、必要経費として一度に計上することはありません。その資産を実際に使用した年ごとに、購入金を「その資産の使用可能な年数=法定耐用年数」で割った金額(「減価償却費」)だけ計上していくのです。この会計手続きが「減価償却」です。
車両の減価償却
一般車両の法定耐用年数は、普通車6年、軽自動車4年です。例えば普通車を300万円で経費購入したなら、50万円(300万円/6年)を必要経費(減価償却費)として、毎年計上していきます。
(参照元:e-Gov)
この記事では、仕訳方をシンプルに解説するために、減価償却費を定額法で計算しています。実際は、より複雑な計算方式(定率法)を用いる場合もあります。
減価償却費の計算には他にも様々な選択肢がありますので、ご自身の状況を詳しく確かめたい場合は税理士に一度ご相談ください。
中古車の減価償却
中古車の減価償却の計算には、法定耐用年数ではなく、次のように算出する年数を使用します。まず、購入した中古車が、法定耐用年数を超過したものだった場合は、その法定耐用年数の20%の年数を使用します。
法定耐用年数を超過していない中古車には、「法定耐用年数 – 使用済期間」に、「使用済期間の20%」を足した期間から、1年未満を切り捨てた年数を使用します。※この年数が2年を下回った場合は、2年を使用します。
例えば2年3カ月使用済の軽自動車では、「4 年 – 2年3カ月 = 1年9カ月」に、「2年3カ月×0.2 = 5.4カ月」を足すと約2年2カ月です。したがって2カ月を切捨てた「2年」が、減価償却に用いる年数です。
また購入した中古車に対して、それと同型の新車価格の50%以上の金額をかけて改良を加えた場合は、新品と同じ法定耐用年数で減価償却を計算します。
(参照元:国税庁)
車両売却時の減価償却
減価償却は、車両売却時の仕訳方をどう決めるのでしょうか。まず売却時での車両の帳簿価額は、売却時までの減価償却費の累計額と、車両購入時の価格から算出されます。この帳簿価額についての計上方法が、直接法と間接法です。
ここからは例として、税込330万円で購入した普通車を4年間使用した後に、税込99万円で売却できた場合を考えましょう。購入時のリサイクル預託金は1万円だったとします。以下、法人での取引を想定して解説しますが、個人事業主の場合もほとんど同じです。
直接法
減価償却費は55万円(330万円/6年)で、4年使用したので減価償却累計は220万円です。つまり330万円分の内、220万円分の価値が消費されている、ということです。
したがって売却時には、110万円分の価値が車両に残っていると見なせます。この110万円を価額として計上し、帳簿に明記する方法が直接法です。
帳簿には以下のように計上します。
- 借方に「現預金」として99万円(実際の売却価格)
- 貸方に「車両運搬具」として110万円(車両の帳簿価額)
- 貸方に「預託金」として1万円
貸方の合計金額111万円から現預金99万円を引いた、12万円が損失です。借方の「車両売却損」として、この12万円を記入します。
間接法
対して間接法では、売却時の車両価額自体は計上せず、購入時点での車両の価格(330万円)と、減価償却累計(220万円)とを、それぞれ別個に計上します。
帳簿には以下のように計上します。
- 借方に「現預金」99万円(実際の売却価格)
- 借方に「減価償却累計額」220万円を計上
- 貸方に「車両運搬具」330万円(購入価格)
- 貸方に「預託金」1万円
このように、売却時までに使用された分の価額(減価償却累計額)を、借方へ計上することで明記する方法が、間接法です。借方の「車両売却損」には、貸方の合計金額331万円から、借方のここまでの合計金額319万円を引いて、12万円を記入します。
要因2:消費税
車両売却は課税取引なので、消費税も考慮して帳簿を付ける必要があります(リサイクル預託金は非課税です)。まず税込経理の場合は、実際にやり取りした金額を、現預金や車両運搬具として計上すれば問題ありません。
消費税込99万円で車両を売却できたのなら、借方の「現預金」に99万円と記入します(直接法)。減価償却を間接法で処理するなら、貸方の「車両運搬具」には、車両購入時に支払った消費税込金額330万円を記入します。そして貸方の「預託金」に1万円を記入します。
税抜
税抜の場合、記入事項が増えます。まず借方の「現預金」には、税込売却金額99万円を記入します。税抜記入でポイントとなるのは、現預金99万円の内の消費税分9万円を抜き出し、貸方に「仮受消費税」として計上することです。
減価償却を間接法で記入しているなら、車両購入時の金額も税抜で300万円と考え、減価償却費も50万円(300万円/法定耐用年数6年 )と考えます。したがって借方の「減価償却累計額」に200万円(減価償却費50万円×車両使用期間4年)、貸方の「車両運搬具」に300万円、と記入します。貸方の「預託金」は非課税のため、1万円で問題ありません。
税込でも税抜でも、貸方の合計から、ここまでの借方の合計を引いた金額が、「車両売却損」額となりますので、借方へ記入しましょう。なお税抜と税込とで、この額は異なります。しかし決算時に、税込経理での消費税が租税公課として処理されることでつじつまが合い、結局は税込でも税抜でも、同じ損益額になります。
(参照元:国税庁)
要因3:法人か個人事業主か
先述まで、法人の借方「車両売却損」としていた項目は、個人事業主の場合「事業主貸」に変わります。個人事業主では「事業用固定資産(車両)を、法人(買取会社)へ譲渡した」ことになるため、上記(直接法、間接法)の12万円を売却損ではなく、譲渡損と捉えるからです。
売却益が出た場合、法人の「車両売却損」は「車両売却益」に変わりますが、個人事業主の「事業主貸」は「事業主借」に変わります。
(参照元:貸借対照表作成の手引き)
仕訳方一覧
ここからは、先述の3要因による8パターンの仕訳方を、一括提示します。ご自身の状況に合わせてチェックしてみてください。
直接法の場合
まずは直接法の場合を見ていきましょう。
税込
パターン1-1 (法人)
- a:実際の車両売却金額(税込)
- b:(x + y) – a の金額
※売却益が出た場合は、この計算結果は0未満になります。その場合、ここの「車両売却損」を「車両売却益」に変更し、計算結果の値からマイナス記号を除いた数値をbに記入してください。以下全パターンで同様です。
- x:車両購入時の金額から、売却時での減価償却累計額を引いた金額(税込)
- y:車両購入時に支払ったリサイクル預託金額
※リサイクル預託金は非課税なので、税込でも税抜でも、金額は同じです。
パターン1-2 (個人事業主)
法人の場合と変わりませんが、bの項目が「事業主貸」に変わります。売却益(厳密には譲渡益)が出た場合は、「事業主借」となります。以下全パターンで同様です。
税抜
パターン2-1 (法人)
- a:実際の車両売却金額(税込) ※税抜ではありません。
- b:(x + y + z) – a の金額
- x:車両購入時の金額から、売却時での減価償却累計額を引いた金額(税抜)
- y:aの消費税分の金額
- z:車両購入時に支払ったリサイクル預託金額
パターン2-2 (個人事業主)
bの項目が「事業主貸」になります。
間接法の場合
続いては関節法の場合をチェックしましょう。
税込
パターン3-1 (法人)
- a:実際の車両売却金額(税込)
- b:車両売却時での、減価償却費の累計額(税込)
- c:(x + y) – (a + b) の金額
- x:車両購入時の金額(税込)
- y:車両購入時に支払ったリサイクル預託金額
パターン3-2 (個人事業主)
cの項目が「事業主貸」となります。
税抜
パターン4-1 (法人)
- a:実際の車両売却金額(税込) ※税抜ではありません。
- b:車両売却時での、減価償却費の累計額 (税抜)
- c:(x + y + z) – (a + b) の金額
- x:車両購入時の金額(税抜)
- y:aの消費税分の金額
- z:車両購入時に支払ったリサイクル預託金額
パターン4-2 (個人事業主)
cの項目が「事業主貸」になります。
譲渡所得(個人事業主)の所得税
個人事業主で売却益が出た場合、その年の「譲渡所得」として他の事業所得と通算して申告します。この譲渡所得には50万円の特別控除が適用されます。言い換えると、車両売却益を含んだ譲渡所得が50万円を超えると、課税されるのです。
また5年以上事業に使用した資産(車両を含め)の売却益は、長期譲渡所得へ通算できます。長期譲渡所得では、その1/2の金額しか、所得税の対象となりません。よってもし課税されたとしても、その金額を抑えることができます。
ナビクルの一括査定でより具体的な売却損益を想定しよう

ここまで車両売却の際の仕訳方をみてきました。さらに実際の売却損益をより具体的に想定するため有用なのが車両買取の一括査定サイトです。
最高10社の査定を無料で比較できるナビクルは、簡単な入力ですぐに申し込みが可能で、相場額も即座に教えてくれます。買取会社により査定には数10万円の差が出ることもありますので、ぜひご活用ください。
ナビクルで一括査定するまとめ

減価償却についてからはじまり、仕訳のポイントとなる3つの要因についてお伝えしました。この3要因をおさえ、仕訳方を明確に整理してみましょう。
一見すると複雑な仕訳ですが、後半の8つの仕訳方のまとめも活用すれば、より理解しやすいはずです。
もちろん、売却損をなるべく抑えるためには、少しでも高く車両を売却することが大切です。一括査定サイトを利用するなどして、数社で査定してもらうようにしましょう。
 sirasaka / 編集長
sirasaka / 編集長
弊社マーケットエンタープライズが運営する総合買取サービス「高く売れるドットコム」にて査定業務や出張買取などに携わり、現場で培ったリアルな知見を活かし「満足できる買取体験」を提供すべく買取メディアの運用も行っています。 利用者様の買取にまつわる疑問を解決できる有益な発信のため、日々精進してまいります! リユース営業士資格保有(日本リユース業協会より授与)
関連キーワード