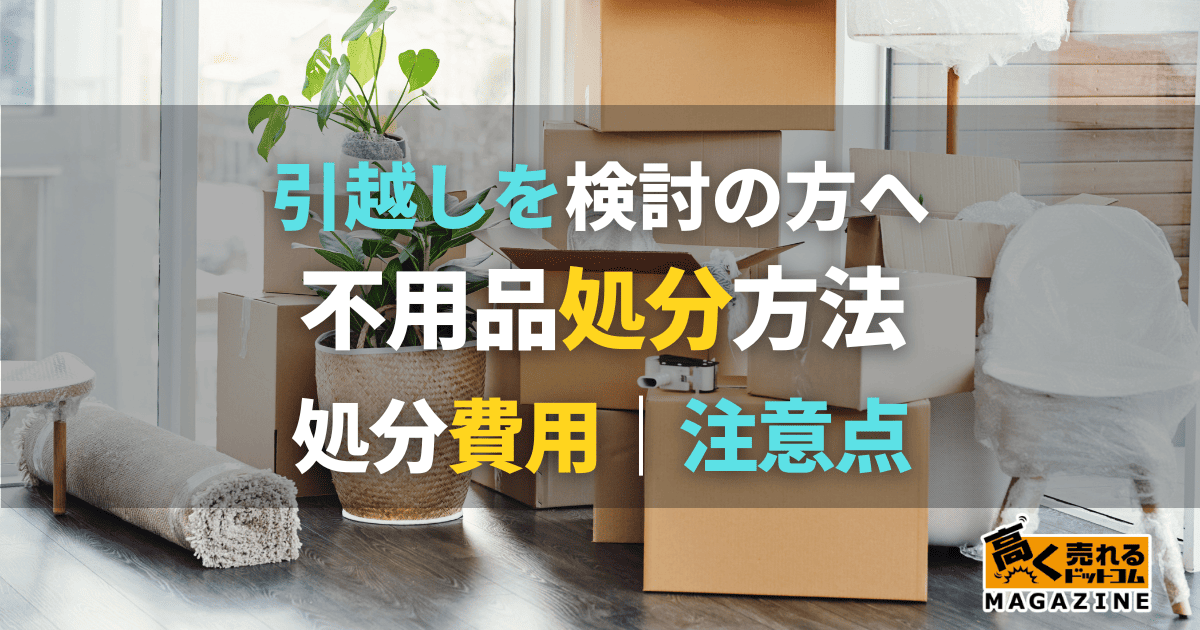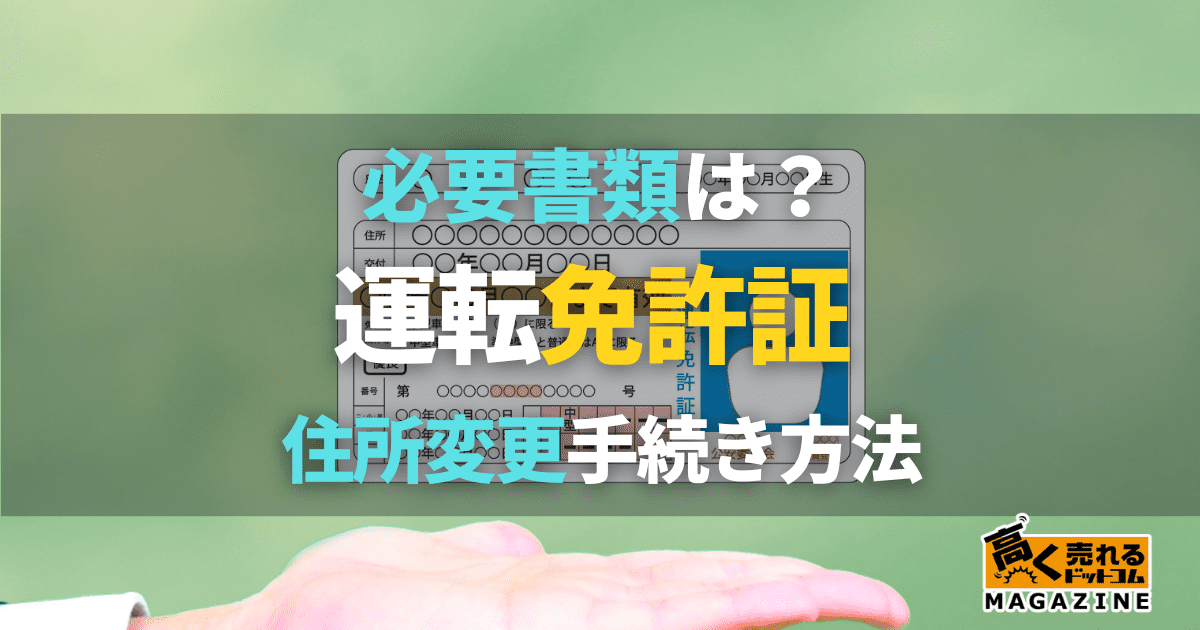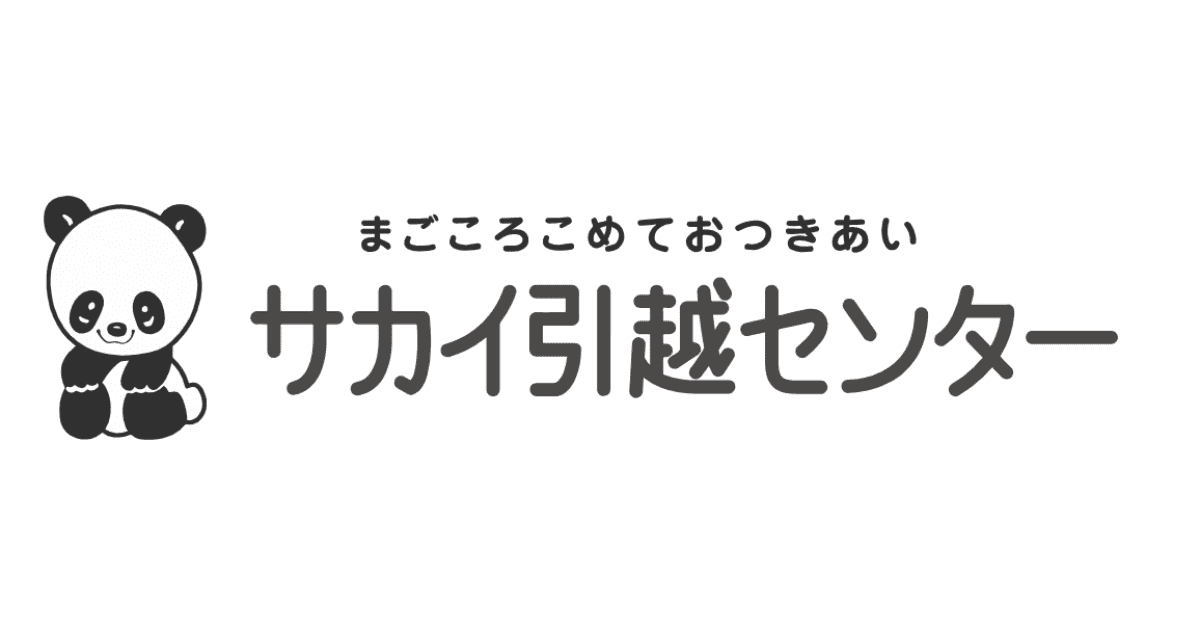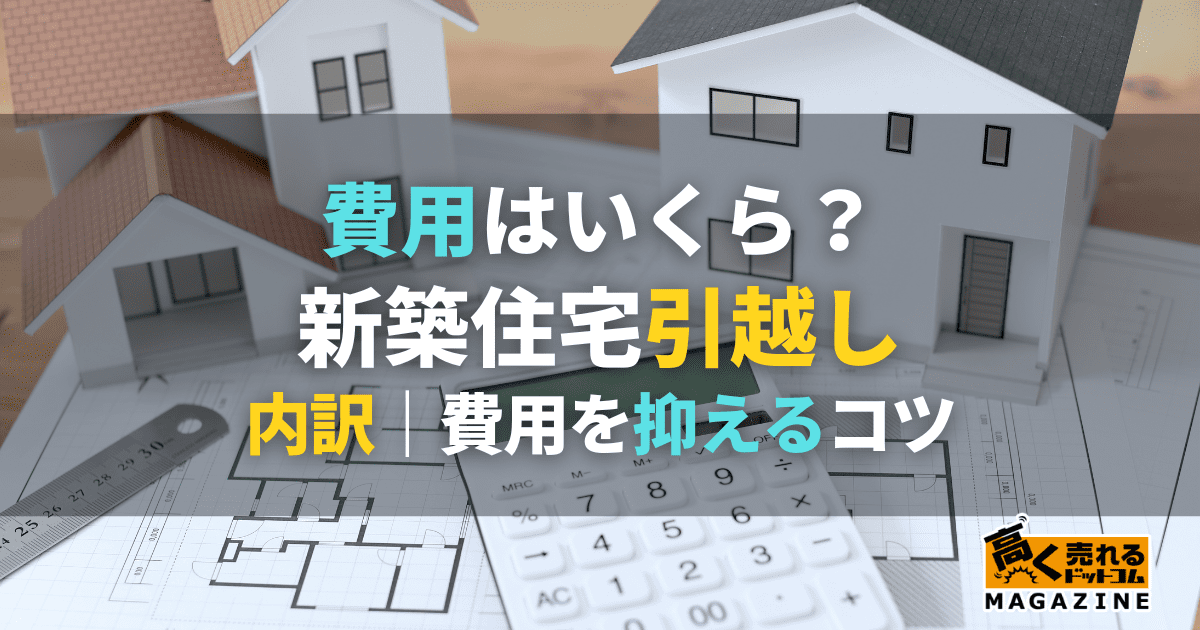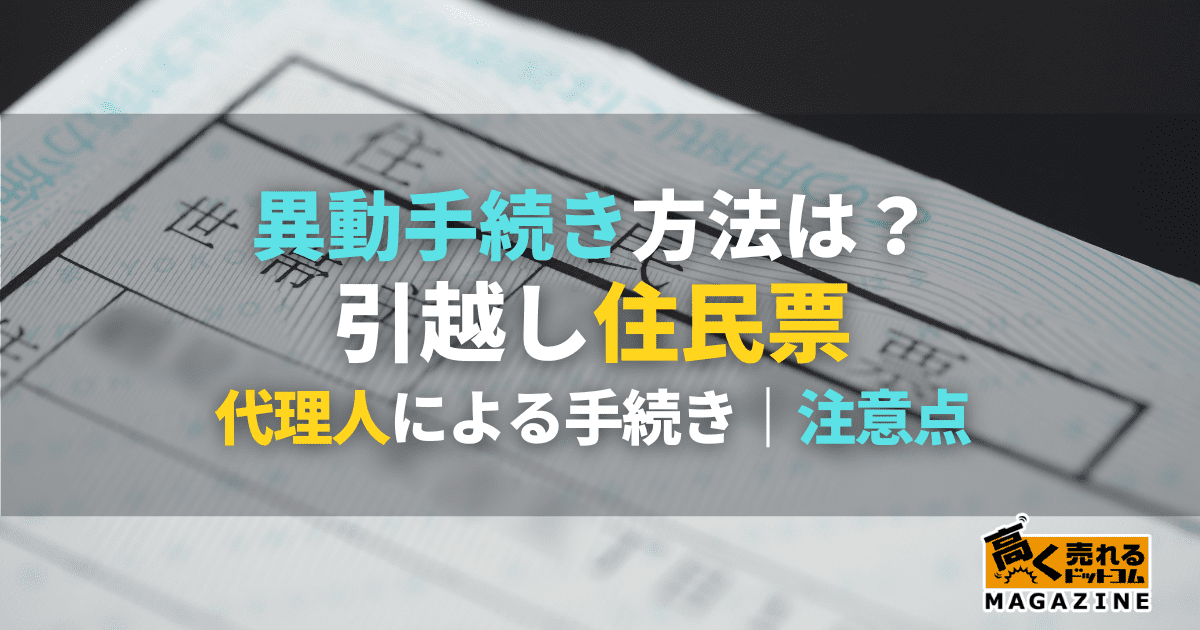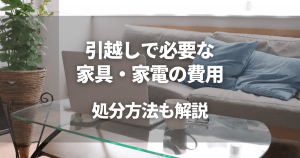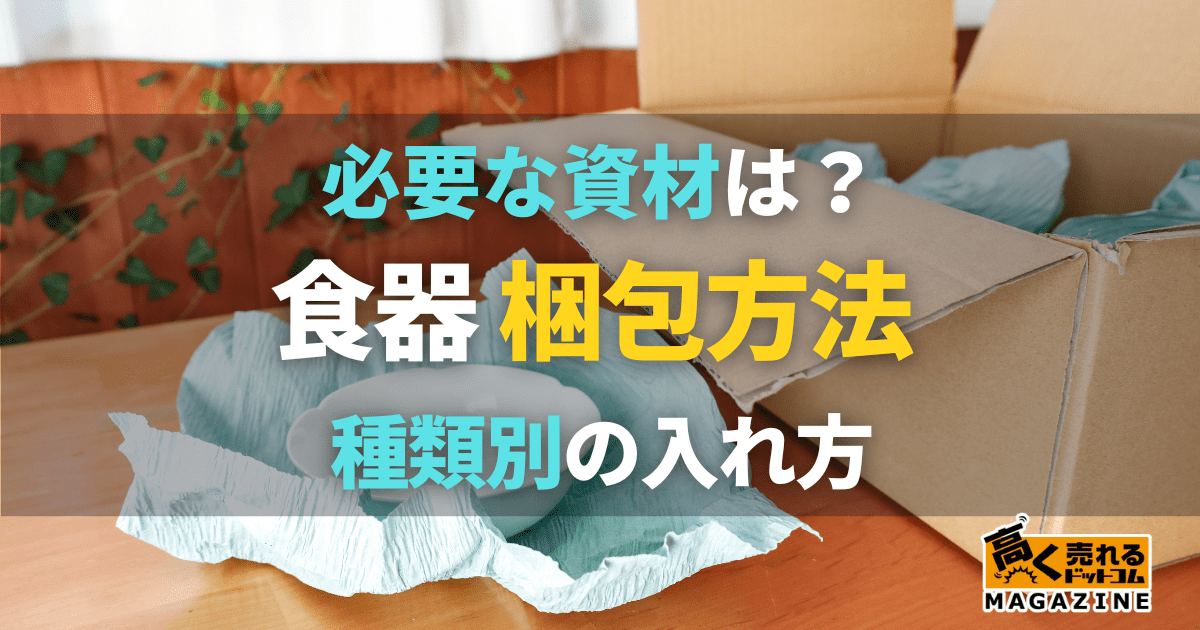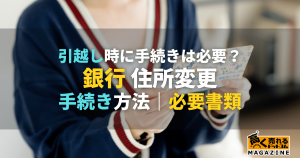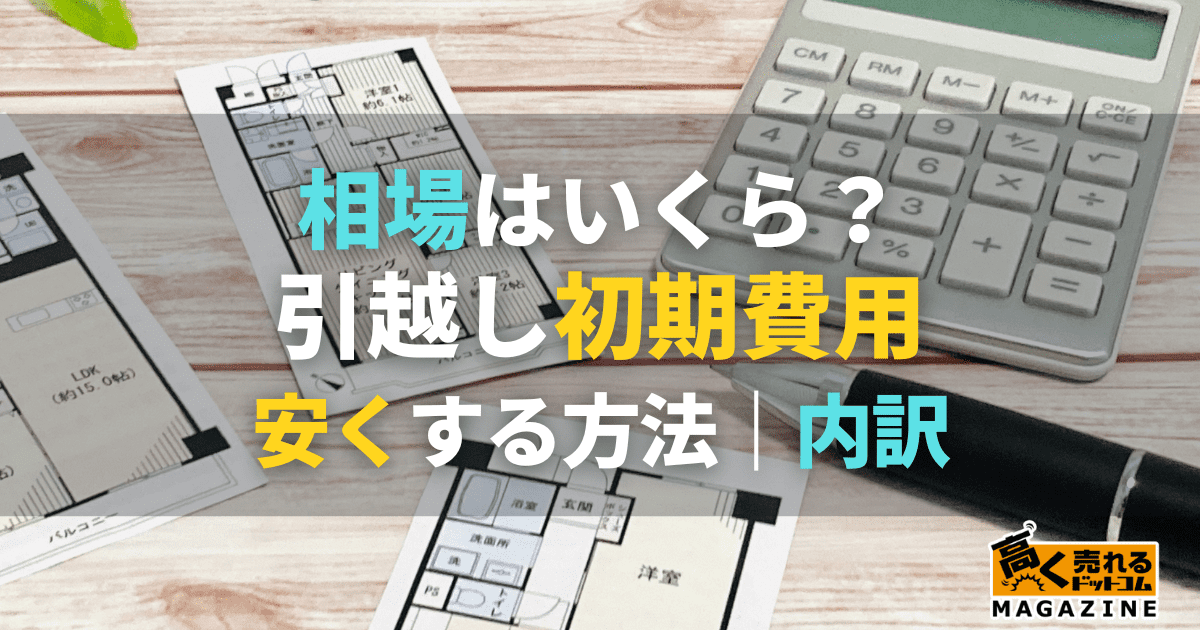- 引越しおすすめ
引越し手続きの順番とチェックリスト!転出・転入・転居届(住所変更)など
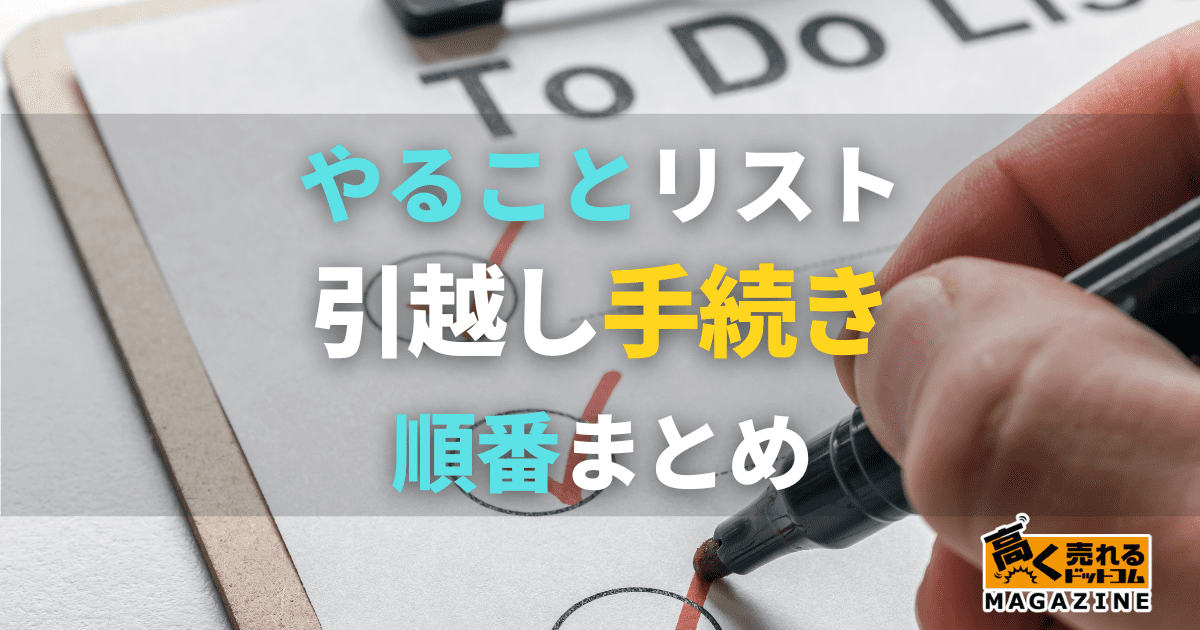
※当記事はアフィリエイト広告を含みます。
※「高く売れるドットコム」「おいくら」は弊社マーケットエンタープライズが運営するサービスです。
引越しを行う場合、さまざまな手続きが発生します。役所への届けに始まり、電気・ガス・水道などの停止や開始、ゴミの処分や免許証の住所登録、車を持っている場合は運輸支局などへの報告など。
その数は非常に多く、手続きを行う先も多岐にわたります。計画的にそれぞれの手配を行わなくてはなりません。
本記事では、いつ、どんな手続きをしたらよいかを時系列でまとめてご紹介いたします。
ぜひ全体の流れを把握して、手続きに漏れが生じないよう、計画的に引越しの段取りを進めましょう。
※買取相場は執筆時点で取得した情報となりますので、実際の買取価格と異なる可能性がございます。
引越し前に早めに行うべき手続き

引越しが決まったら、その日まで時間があっても早くからやっておいた方がいい手続きがあります。目安として、1ヶ月以上前の時点で済ませておきたい手続きをご紹介いたします。
1.賃貸物件の解約
住居が賃貸住宅の場合、前もって退去を通告しておく義務があります。
実際は契約書に記載されている内容が適用されますが、1~2ヶ月前には解約を申し出るよう定められているのが一般的です。
引越しの日にちが決まったら、住居の管理会社や大家さんに早めに連絡を入れましょう。
その際、敷金がいつ、どの程度返ってくるか、退去する月の家賃が日割り計算されるのかなども確認しておくと、後でトラブルが起きることを抑止できます。
2.駐車場の解約
駐車場を月極で契約している場合も、住居と同様、事前に解約のための連絡を行う必要があります。
連絡が遅くなると、次の車が決まるまでの期間の駐車料金を請求されてしまう恐れもあります。
3.子どもの転校や転園
公立の小中高校に通う子どもがいる場合、転校のための手続きを行う必要があります。まずは担任の先生に引越しが決まったことと、その日付を伝えます。
その後、学校から「在学証明書」と「教科書給与証明書」を受け取ります。
私立の学校や高校に通っている場合は、編入試験を受ける必要も出てくるので、転居先の教育委員会や希望する学校に問い合わせをしておきます。
子どもが保育園や幼稚園に通っている場合も、引越しをすることを伝えた上で、転居先で通う受け入れ先を探します。地域によっては待機児童の問題もあるため、できるだけ早く動くようにしてください。
4.収入証明書の入手
収入証明書は、ローンの利用や保育園の利用にあたって必要となる書類です。記載事項を変更するのに時間がかかりますので、早めに手配しておいた方が安心です。
会社に勤めている人は、総務に新しい住所を連絡すれば手続きを代行してくれます。また、このタイミングで社内の登録情報の更新や、新しい通勤費の金額などもまとめて会社側と確認しておくとよいでしょう。
5.引越し業者の選定
引越し先と引越し日が決まったら、なるべく早めに業者選定をしましょう。
さまざまな業者の中から1つを選ぶのは難しいので、ぜひ一括見積りサービスを利用して最良の業者を探してください。
SUUMO引越し見積もり

SUUMO引越し見積もりは、オンラインで複数の引越し業者へ一括で見積もりを依頼できるサービスです。
口コミ情報をチェックしながら見積もりを依頼できる会社を選択でき、希望する日にもっとも安く作業してくれるところを見つけられます。
選べる引越し業者は、SUUMO引越し見積もりが厳選した会社ばかりであるため、安心です。会社とはメールでやり取りができます。
電話番号の入力も不要であるため、一括見積もりサイトにありがちな、営業電話がたくさんかかってくるといったこともありません。
引越し1ヶ月前に行う手続き

ここから先は引越しまでの1ヶ月間で順次済ませておきたいことを紹介していきます。
1.プロバイダーへの連絡
自宅でインターネット回線を利用している場合はプロバイダーに連絡をして、転居の手続きをしておきます。
引越し後も同じ業者を使う場合は連絡のみとなりますが、新居がマンションなどで既に回線がある場合などは、解約をすることになります。
新居に回線設備がない場合は、開通のための手配も必要です。春の繁忙期など、時期によっては開通まで時間がかかることもあるため、早めの手配がおすすめです。
また、引っ越しを機に料金を見直すのもおすすめです。以下の記事が参考になるかもしれません。
引っ越し先のWiFiはどうする?導入の手続き方法や注意点を解説
2.粗大ゴミの処分
粗大ゴミの定義は自治体によって異なりますが、いずれにしても一般のゴミとは違って、別料金がかかってきます。
また、事前に自治体に申し込みをして、処分にかかる費用を支払っておくのが一般的です。
それでも春の繁忙期は順番待ちになったりすることもあり得ます。引越しまで1ヶ月を切ったら、不要な粗大ゴミの処分に手をつけるようにしましょう。
なお、エアコンやテレビなどは、原則として購入した店舗に引き取りを相談するようにしてください。
▼引越しの際の不用品の処分方法については、こちらの記事に詳しくまとめています。あわせてご覧ください。
3.火災保険や地震保険
現在、火災保険や地震保険に加入している場合、転居先の住宅に合わせたプランに変更する必要が出る可能性があります。
その場合、検討期間が必要になることもありますので、まずは連絡をした上で、保険会社と相談するようにしてください。
引越し2週間前に行う手続き
このタイミングでのポイントは、役所に関する手続きが可能になるということです。
何回も足を運ぶのは大変ですから、まとめて複数の手続きをするようにしてください。
同じ自治体内で引越しをする場合は、必要ありませんので、次のパートに進んでいただいてかまいません。
1.転出届の提出
新居の場所が現在と異なる自治体にある場合は、住民票を移すために転出証明書が必要になります。
転出証明書は、今住んでいる自治体に転出届を出すことで発行してもらえます。転入するときに必要となるので、なくさないように保管しましょう。
転出届は一般的に、引越し当日の14日前から受け付けられます。それに合わせて、以下に紹介する他の手続きを済ませてしまうと効率的です。
2.国民健康保険の資格喪失
国民健康保険に加入していて、今と異なる自治体に転居する場合は、現在の健康保険についての資格喪失の手続きが必要となります。
これは国民健康保険が自治体単位で運用されているからです。いったん資格を喪失させた上で、転居先の自治体が運用する保険にあらためて入ることになります。
なお、会社などで健康保険に加入している場合は、会社が必要な手続きを代行してくれますので、個人で行う必要はありません。
3.印鑑登録の抹消
印鑑登録に関しては、今住んでいる自治体の役所に登録するため、現在の登録はひとまず廃止しておきます。
なお自治体によっては、転出届と同時に印鑑登録も自動で廃止してくれることもありますので、窓口で確認するようにしてください。
4.児童手当の住所変更
児童手当も各自治体が運用している制度です。そのため、異なる自治体に転居する場合は現在の住居のある役所で児童手当受給事由消滅届を提出しましょう。
代わりに前年度の所得や課税金額を証明する所得課税証明書を受け取ります。
5.介護保険の住所変更
異なる自治体に転居する場合、現在発行されている介護保険被保険者証を返納します。
それと交換して受け取るものが、介護保険受給資格証です。これを転居先の自治体に提出することで、新しい被保険者証を発行してもらいます。
6.原付(50~125ccのバイク)の登録変更
50~125ccの小型バイクを所持している場合は、各自治体が登録変更の窓口になります。
そのため、他の自治体に移動する場合、今の役所にバイクのナンバープレートを返却し、代わりに廃車証明書を受け取る手続きが必要になります。
ただし、新居までバイクに乗って行きたい場合は、引越し先の役所で廃車の手続きと、新しい登録をセットで行うことが認められています。
7.ペットの登録事項
犬や猫など国の指定動物をペットとして飼っていて、現在と異なる自治体に転居する場合は、登録情報を更新する必要があります。
役所か保健所で、登録事項変更届を提出し、代わりに鑑札と、犬の場合は予防注射をしていることを証明する注射済票を受け取ります。
引越し2週間前に行う手続き【ライフライン編】
ここから先は、引越し先の場所を問わず、誰にとっても必要な手続きが目白押しです。ひとつひとつ確実に済ませていきましょう。
1.電気の使用停止と開始
現在使っている電気の利用を停止するための手続きを行います。手続きは、電力会社やガス会社のウェブサイトから行うことができます。
その際、利用明細に書かれているお客様番号が必要となります。利用の停止にあたっては、原則として立ち会う必要があるため、引越しの当日の作業時間を考え、時間を設定しておきます。
最後の月の料金は日割りとなります。立ち合った際に支払うほか、口座振替やカード払い、新居への請求書送付も選択できます。
2.ガスの使用停止と開始
現在使っているガスを閉栓するための手続きを行います。手続きは、ガス会社などのウェブサイトから行うことができます。
転居先でも同じ会社を使う場合は、同時に利用開始の手続きもしておきましょう。会社が変わる場合は、別途、開栓のための手続きをしておきます。
ガスは利用を始める場合に必ず立ち会いが必要となるため、忘れてしまうとその日はガスが使えなくなることもあります。
引っ越しは固定費を見直すのに絶好のタイミングです。自分に合った電力会社やガス会社に乗り換えて生活費を抑えられないかチェックしてみませんか?
▼こちらの記事では、おすすめの電力会社やおすすめのガス会社が紹介されています。ぜひご一読ください。
・おすすめの新電力会社はこちら
・おすすめのガス会社はこちら
3.水道の使用停止と開始
現在使っている水道の利用を停止する手続きを行います。連絡先は地域を管轄する水道局や事業会社です。
地域によっては上水道と下水道の運営が異なる場合もあります。
4.郵便物の転送
全国の郵便局では、引越しをしてから1年間、新しい住所に郵便物を転送してくれるサービスを提供しています。
ただし、手続きをしてから反映されるまでに1週間程度かかります。手続きの際には、運転免許証などの本人確認書類が必要です。
引越し先へ転送してくれるのは1年間
転送してくれるのは1年間のみなので、銀行やクレジットカード会社からの明細については住所変更を忘れても転送してくれますが、更新を忘れたまま2年目に突入してしまうと明細はもちろん届きません。
転送されなくなり、銀行やカード会社からの郵便物が届かなくなると、例えばキャッシュカードでお金が引き出せない、口座を止められるなどのトラブルに発展することもあります。
銀行などへの住所変更も余裕を持って行っておきましょう。
5.固定電話の変更
自宅で利用している電話回線のサービス会社に住所変更を連絡します。ウェブサイトから申し込めるほか、NTTの場合、電話番号116でも受付をしてくれます。
春の繁忙期は新しい電話番号への切り替えに時間がかかることもあるので、早めに連絡しておきましょう。
特に転居先での工事の手配が重要ですので、引越しした当日に予約が取れればベストです。
6.携帯電話の変更
固定電話と異なり、携帯電話やスマートフォンの場合は、住所が変わっても番号が変わることはありません。
しかし、必要な書類が届かなくなるなどの問題がありますので、引越しをしたタイミングで住所変更の手続きをしましょう。各社のウェブサイト上からできるほか、店頭でも手配が可能です。
引越し後に行う手続き

引越しをした後は、転居先での手続きがたくさん待っています。手続きを忘れてしまうと罰金を取られてしまうこともあるので、注意しましょう。
1.転居届と転入届
同じ自治体の中で引越しをした場合は、役所に転居届を提出します。転居届は引越しをした日から14日以内に届け出ることが義務付けられています。
また、別の自治体に引越しをした場合は、転入届を提出します。こちらも引越ししてから14日以内に届け出を行い、その際、元の自治体の役所で受け取った転出証明書も添付します。
なお、転入届と合わせて、国民年金や印鑑登録などの手続きもまとめて行うと効率的です。
2.印鑑登録
同じ自治体の中で引越しをした場合は、転居届を提出すると印鑑登録に関する情報は自動で更新されます。別の自治体に引越しをした場合は、新たにその自治体の役所で印鑑登録を行います。
3.国民年金
自営業などで国民年金第1号被保険者にあたる場合、引越ししてから14日以内に役所で住所変更の手続きが必要です。ただし自治体によっては転入届などから自動で対応してくれることもあるので、確認してください。
会社などで厚生年金などに入っている場合は、手続きを代行してもらえますが、その際、年金手帳の提出を求められることがあります。
4.国民健康保険の加入
年金と同じく、自営業などで第1号被保険者にあたり、別の自治体に引越しをした場合は、引越ししてから14日以内に役所で住所変更の手続きが必要です。
手続きを忘れると新しい保険証を受け取ることができないため、医療費が全額負担になる可能性があります。
5.児童手当
同じ自治体の中で引越しをした場合は、転居届を提出すると児童手当に関する情報も自動で更新されます。
別の自治体に引越しをした場合は、元の自治体の役所で受け取った所得課税証明書と児童手当認定請求書を提出します。こちらは、引越しの日から15日以内に手続きを行う必要があります。
6.介護保険
別の自治体に引越しをした場合、介護保険受給資格証を提出し、要介護・要支援認定を申請します。
7.学校の転校
新しい住民票を教育委員会に提出すると、入学通知書を受け取れます。
これと在学証明書、教科書給与証明書を合わせ、転校先の学校へ提出します。ただし地域や学校によって手続きが異なる場合もあります。
8.ペットの登録事項
別の自治体に引越しをした場合、30日以内に鑑札と予防注射済証を役所か保健所に提出します。同じ自治体の中で引越しをした場合は、転居届から自動で更新されるので手続きは不要です。
9.運転免許証と車庫証明
運転免許証は警察署、運転免許センター、運転免許試験場などで、記載事項変更届を提出します。更新期間内に引越しをした場合は、通常の免許更新に合わせることもできます。
車庫証明が必要な場合は、引越しから15日以内に、管轄の警察署に保管場所証明申請書を提出します。
手続きは、運転免許や車庫証明に関する住所変更の注意点をまとめた下記の記事を参考にしてください。
また、車検証の住所変更手続きも忘れずに行いましょう。
車検証の住所変更を忘れてしまうと、自動車税の支払通知が届かないため、自動車税を滞納してしまうリスクもあります。
さらに、自賠責保険が下りない可能性もありますので、もしもの時のためにも手続きをしておきましょう。
10.自動車、バイク、自転車
自動車と126cc以上のバイクは管轄の運輸支局で、軽自動車は軽自動車検査協会で、いずれも引越しをしてから15日以内に住所変更の手続きをします。
原付(50~125ccのバイク)は役所で手続きを行います。
自転車を引越し先に持っていく場合は、防犯登録の抹消と変更が必要です。
防犯登録の抹消はその自転車を購入した店舗や警察署で手続きができます。
引越し後は、新しい地域での防犯登録の変更手続きまで必ず行いましょう。
まとめ
引越しにはさまざまな手続きが伴います。転入届や転出届、電気・ガス・水道などの停止や開始、ゴミの処分や免許証の住所変更など…。
それらを全てまとめて行おうとしたら大変です。計画的に順次済ませていくことが肝心です。
 sirasaka / 編集長
sirasaka / 編集長
弊社マーケットエンタープライズが運営する総合買取サービス「高く売れるドットコム」にて査定業務や出張買取などに携わり、現場で培ったリアルな知見を活かし「満足できる買取体験」を提供すべく買取メディアの運用も行っています。 利用者様の買取にまつわる疑問を解決できる有益な発信のため、日々精進してまいります! リユース営業士資格保有(日本リユース業協会より授与)
関連キーワード